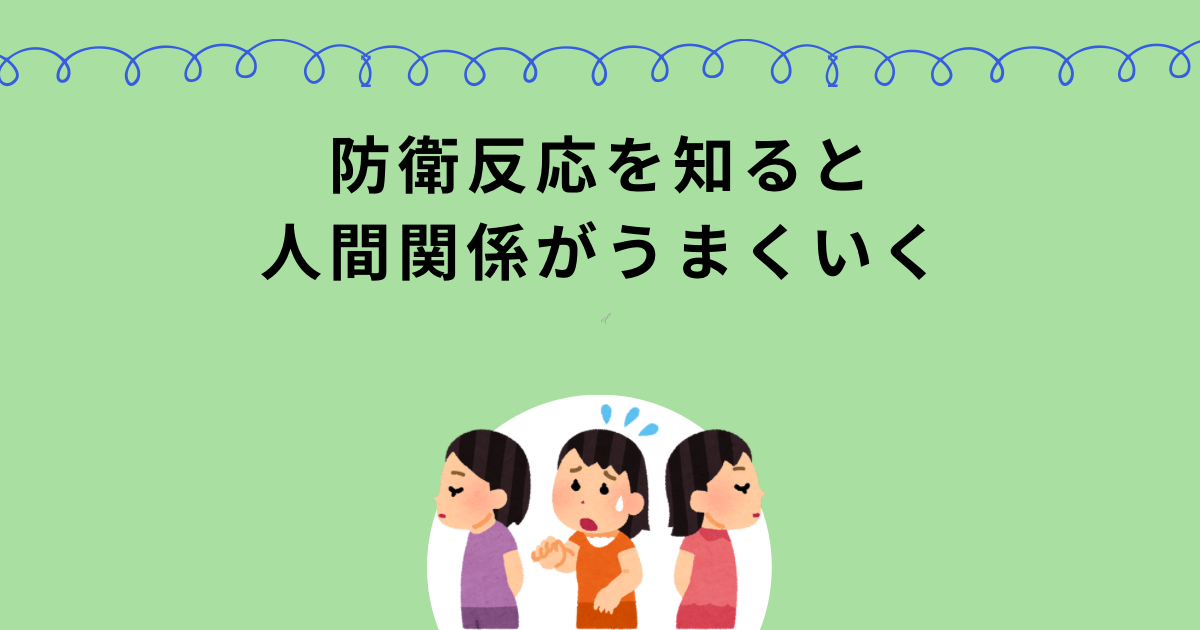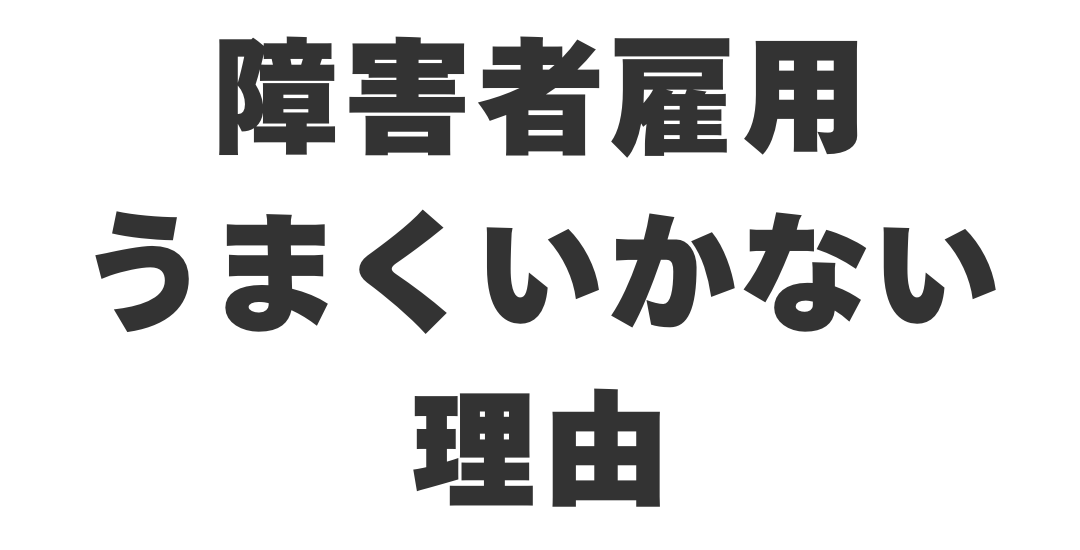本人の防衛反応を理解する──現場で見る4つの事例と対応
支援の現場では、「反発的」「扱いにくい」「空気が読めない」といった言動に日々直面することがあります。
それらの多くは「本人の問題」とされがちですが、実は背景に“防衛反応”があるケースが少なくありません。
本記事では、企業や特例子会社での支援現場で見られる防衛反応を4つの事例で構造的に理解し、
「なぜその行動を取ったのか」「何を守ろうとしていたのか」から考える支援の視点を提示します。
① 知ったかぶり──確認も報告もしないのは「傷つきたくない」から
本人の中で起きていること
過去に「知らない」と言ったとき、「なんでそんなことも知らないの?」と叱られた経験がある。
家でも学校でも、「できる子」として振る舞うことを求められ、「質問する=劣等感の露呈」と刷り込まれてきた。
本人にとって“知っているふり”は、自尊心を守る最後の砦だった。
防衛反応の構造
- 報告・相談・質問が「無能だと思われる」リスクと結びついている
- できないことを認めるより、表面的に取り繕うことで安定を保とうとする
支援者が感じやすいこと
- 「なぜ聞いてこないの?」「確認すればいいのに」とイライラする
- 誠実さがないと感じ、信頼を持ちづらくなる
対応のヒント
- 「わからないことを言っても関係は壊れない」経験を意図的に積む
- 報連相を“信頼関係をつくる行為”として位置づける
- 「報告してくれて助かった」と言葉にして伝える
② 反論・食ってかかる──「自分を守るには攻めるしかなかった」
本人の中で起きていること
学生時代、先生や親から一方的に否定される経験が繰り返された。
反論しなければ、自分の意見も気持ちも無視された。
「従う=自分を失う」だった。だから大人になっても、“先に攻撃する”ことで存在を守っている。
防衛反応の構造
- 指示や助言=支配・否定と受け取り、過剰に反応する
- 正しさを主張することで、自分の尊厳を守ろうとしている
支援者が感じやすいこと
- 「素直じゃない」「議論ばかりしてくる」と対応が面倒に感じる
- 関係性が築けないと判断して、距離を置きたくなる
対応のヒント
- 相手の反論を“防衛”と捉え、まずは受け止める
- 「どう思う?」と主導権を渡す構造を意識する
- 結論よりプロセスを共有する姿勢で信頼を築く
③ 空気を読まない発言──「どうせ嫌われるなら、自分を出した方がいい」
本人の中で起きていること
子どもの頃から“普通にふるまえない”ことで笑われ、否定された。
気を遣っても伝わらなかった。
だから大人になった今、「どうせ浮くなら、自分の言いたいことを言う方が楽」と感じるようになった。
防衛反応の構造
- 場の空気や他人の感情に同調しようとすると、不安や混乱が強まる
- 自分の表現を抑えるより、むしろ“先に出す”ことで支配感を得ている
支援者が感じやすいこと
- 「なぜこんな場面で言うの?」と驚き、困惑する
- 「常識が通じない」と感じて、注意を強めたくなる
対応のヒント
- 本人の言いたかった“本質”に注目し、意図を翻訳する
- 発言のタイミングについてフィードバックする機会を設ける
- 「言っても大丈夫な場」と「言わない方がいい場」の使い分けを一緒に学ぶ
④ 攻撃的・無礼に見える態度──「怒りでしか、自分を守れなかった」
本人の中で起きていること
小さなミスで怒鳴られた、正当な理由があっても話を聞いてもらえなかった。
「自分の正しさを証明しないと、すべて否定される」。
だから怒りを前面に出すことで、相手を遠ざけ、自分の安全を確保している。
防衛反応の構造
- 怒りを使って、他者との距離を調整する
- 自分の傷つきやすさを隠すため、強さを演出している
支援者が感じやすいこと
- 「威圧的で怖い」「関わりたくない」と感じる
- 「何を言っても通じない」と無力感に陥る
対応のヒント
- 怒りの言葉に反応せず、背景にある不安や不信に着目する
- 必要に応じて物理的距離を取りつつ、安全な対話機会を設ける
- 「自分を守ってきた方法としての怒り」と捉え、関係を切らずに関わる
まとめ──「本人の構造」に敬意をもって関わる
ここで紹介した4つの防衛反応は、どれも「困った人の問題」ではありません。
それは過去に傷ついた経験が何度も重なった末に、本人が選び取った「自分を守る技術」です。
支援者がそれを構造として理解できたとき、イライラは共感に変わり、支援が少しずつ機能し始めます。
まずは「この人は、何から自分を守っているんだろう?」という問いを、支援の出発点にしてみてください。