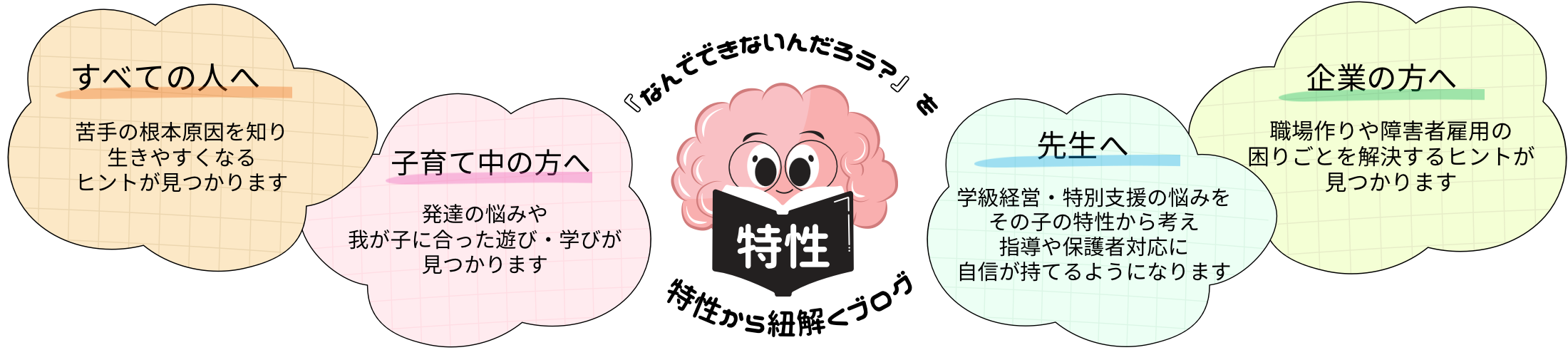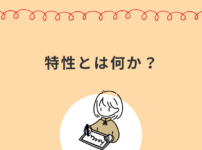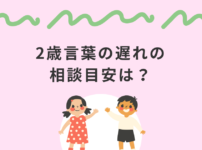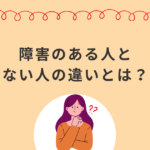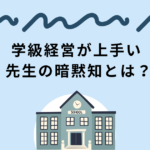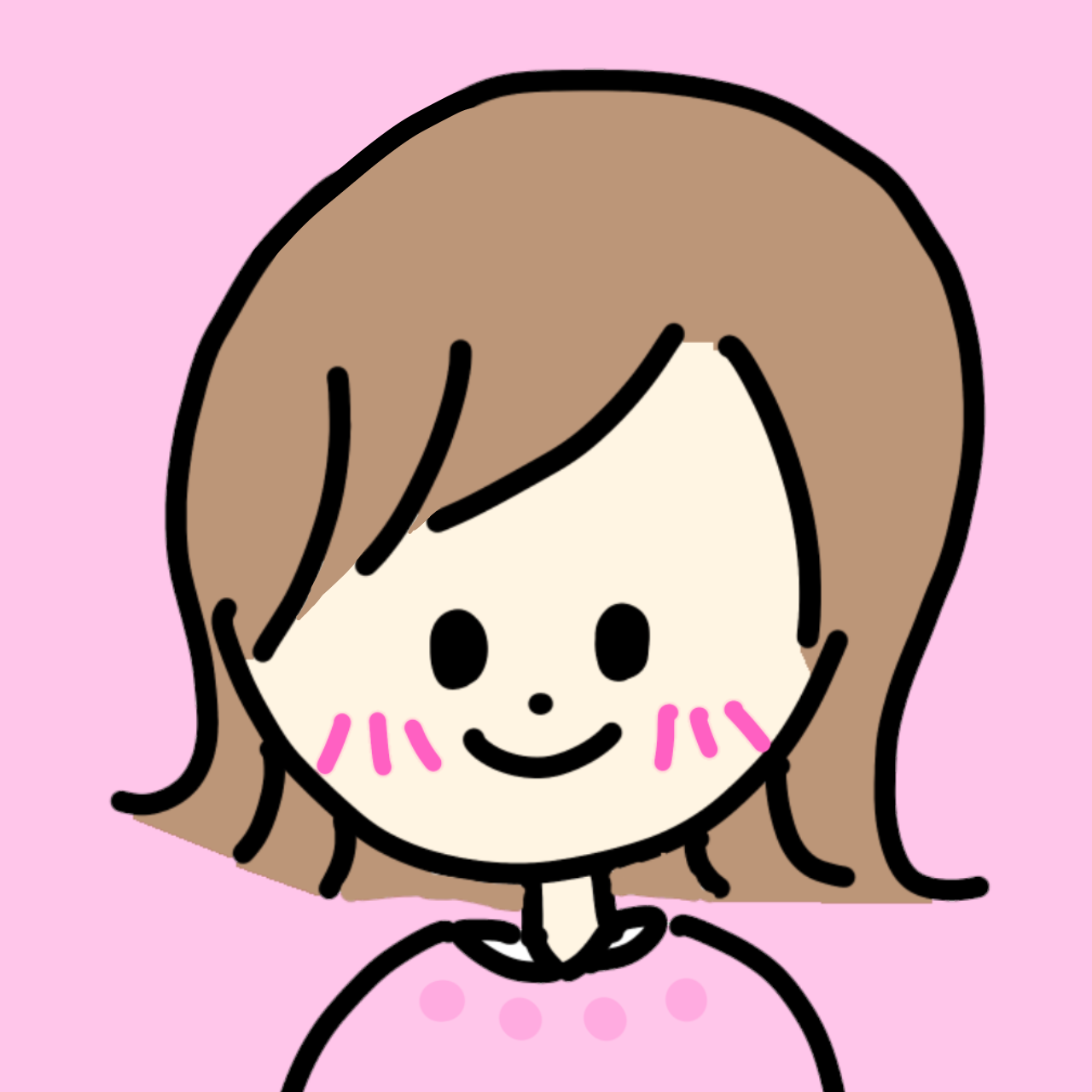
さわり
「なんでできないんだろう?」と悩んでいませんか?
さわり(元特別支援教員)が、見えない特性と根本原因から一緒に考えます。
今、こんなことで困っていませんか?
-

-
【2025年版】後悔しないクリスマスプレゼント|高くても“長く使える”発達と特性に合ったおもちゃ選びガイド
続きを見る
-
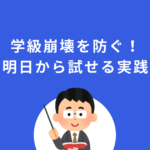
-
学級崩壊を防ぐ鍵は“特性理解”にあり!明日から試せる実践的アドバイス
続きを見る
-
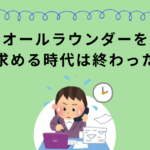
-
オールラウンダーを求めすぎる職場が人材を失う理由|人事・管理職のための「特性ベース職場設計」
続きを見る
最新の記事
子ども・部下・自分に「どうしてできないんだろう」とモヤモヤしている方へ
-
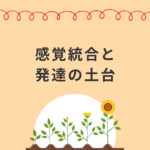
-
『できない』には理由がある。見えない特性を読み解く、感覚統合と発達の土台とは?
続きを見る
カテゴリ
学級経営・特別支援の“正解がわからない”先生のための実践ガイド
-

-
学級経営の悩みを総合的に解決する方法:子どもの行動理解から保護者対応までの完全ガイド
-

-
初任者教員のやりがちな失敗5選|実体験から学ぶ後悔しないためのコツ
-
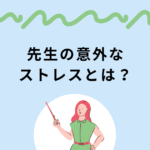
-
先生の見えにくいストレスとは?
「周りと同じペースでは育っていないかも…」と感じたとき、無理に“できるようにさせる”のではなく、自然にできる子育てのアプローチです。
-

-
コップ飲みがなかなか進まないときに見直すこと|いつから始める?発達のサインとステップ
-
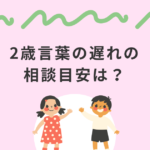
-
2歳言葉の遅れの相談目安は?様子見で終わらせない家庭でできる関わり方
-
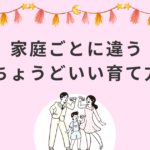
-
親の特性を無視した子育ては続かない。家庭ごとの“ちょうどいい育て方”の見つけ方
社内で浮きがちな障害者雇用を、みんなにとってプラスの仕組みに変えたい担当者へ
-
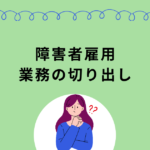
-
任せる仕事がない?障害者雇用で「社内ニート」が起きる理由と業務の切り出し方
-
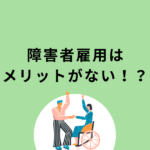
-
障害者雇用はメリットがない?同僚に与えるポジティブな影響とは
-
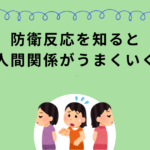
-
本人の防衛反応を理解する──現場で見る4つの事例と対応
-
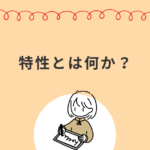
-
特性とは何か — 「平均」とのズレをどう考えるか
2025/12/13
-
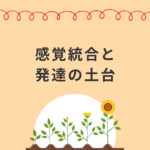
-
『できない』には理由がある。見えない特性を読み解く、感覚統合と発達の土台とは?
2025/11/28
-
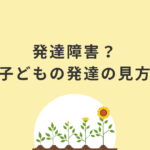
-
子どもの発達を“点”で見ていませんか?月齢より大切な『成長の流れ』を専門家視点で解説
2025/11/17
もっと見る
-

-
初任者教員の服装完全ガイド|入学式・普段着・体育館の靴まで失敗しない選び方
2025/11/18
-

-
学級経営の悩みを総合的に解決する方法:子どもの行動理解から保護者対応までの完全ガイド
2025/11/24
-

-
どうしてこの子は、何度言ってもわからないの?──“特性”の見立てで変わる関わり
2025/4/30
-

-
初任者教員のやりがちな失敗5選|実体験から学ぶ後悔しないためのコツ
2025/11/24
もっと見る
-

-
赤ちゃんが舐めるのはいつまで?止める判断基準とおすすめおもちゃ
2026/1/15
-

-
2歳から始める南海トラフ地震対策|わが家の5年計画と家庭防災の考え方
2025/12/24
-
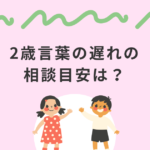
-
2歳言葉の遅れの相談目安は?様子見で終わらせない家庭でできる関わり方
2025/12/13
-

-
おもちゃを買っても遊ばない…なぜ?|支援センターでは夢中なのに家ではスルーな理由
2025/12/3
-

-
冬の自宅保育にぴったり!羊毛フェルトの花のキャンドルホルダーの作り方
2025/12/2
もっと見る
-

-
義足の防災士から学ぶ『障がい者の防災対策』レビュー|企業の防災担当が見落としがちな前提
2025/12/12
-

-
「またか…」と言う前に──失敗を“構造”で捉え直す視点と対処法
2025/5/20
-

-
「できない」は本当に能力の問題?──近くに人がいると動けなくなる現象とその支援
2025/5/13
-

-
なぜ言わなくていいことを言うのか?──衝動性を“扱える形”に変える支援
2025/5/10
-

-
多動性・衝動性は「わがまま」じゃない──現場での支援のヒント
2025/5/4
もっと見る