教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
この記事で伝えたいこと
- 「行動」ではなく行動の背景を理解する姿勢が重要
- 同じ症状名でも子どもによって対応は変わる
- 育児書や診断名だけに頼らず、わが子を見て考えることが大切
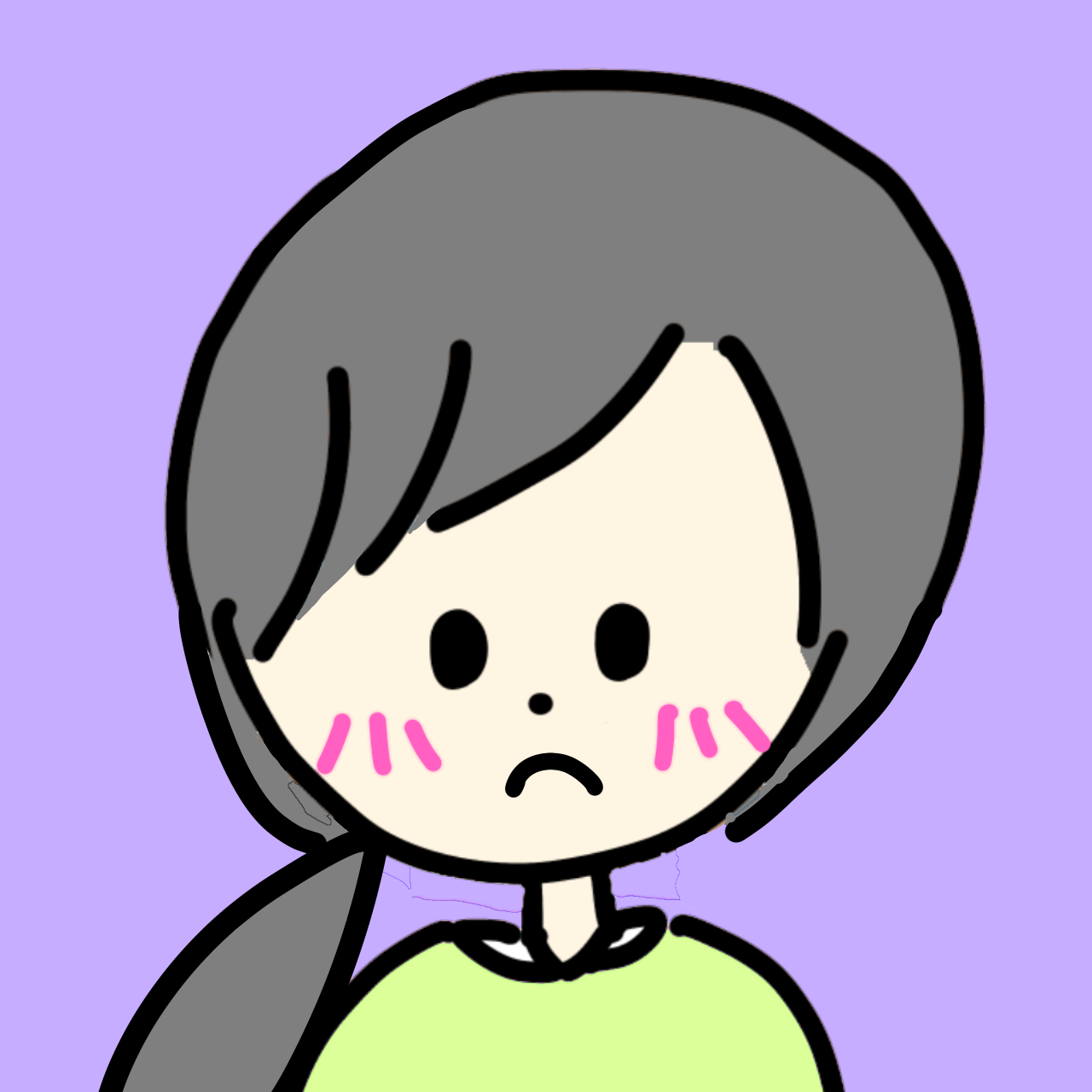
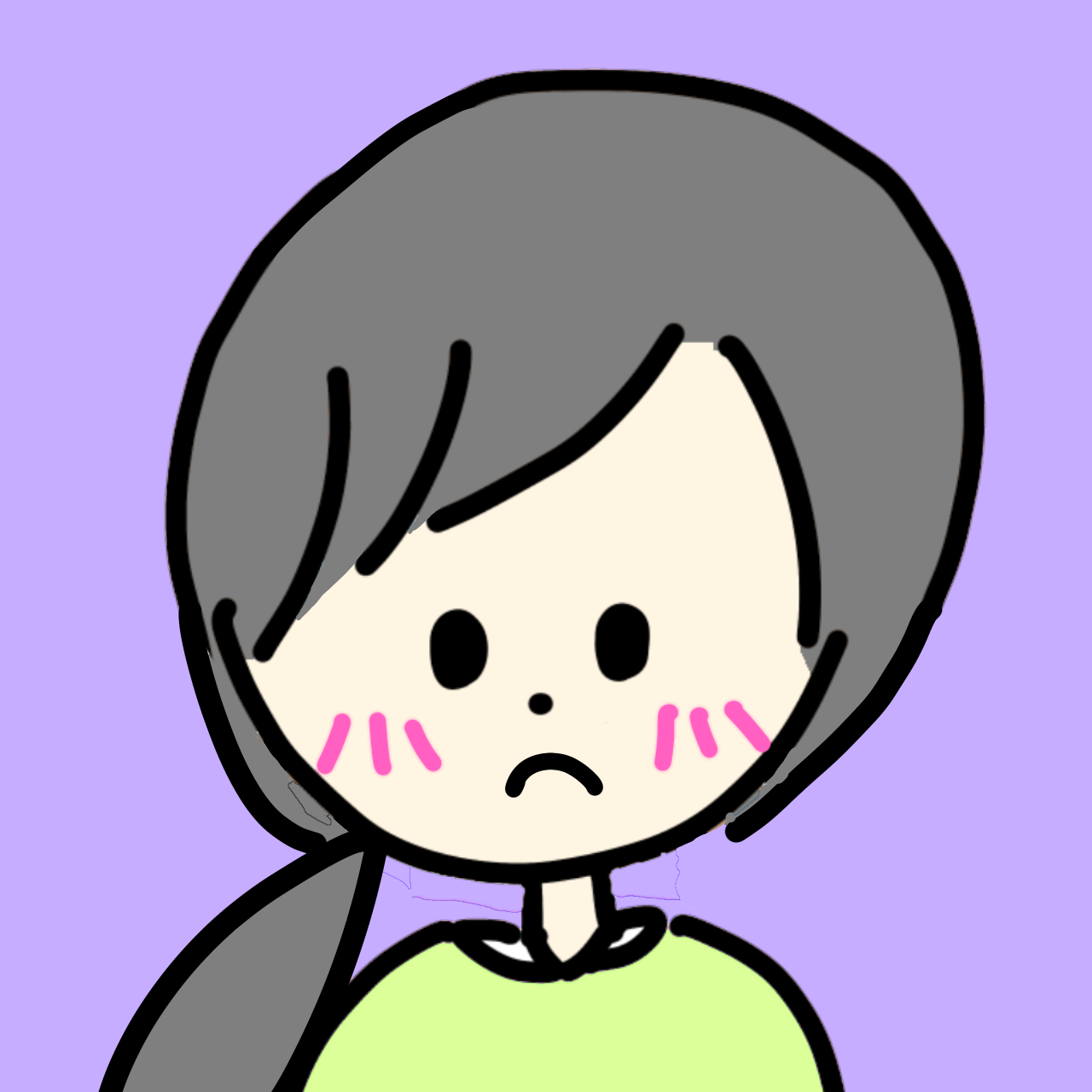
そんな夜が続き、私自身も心身ともに参っていました。
◆ 想像以上に辛い「夜中の泣き叫び」
我が子は2歳頃、以下のような様子でした。
- 夜中、突然起きて泣き叫ぶ
- ただの泣き声じゃない。耳をふさぎたくなるような激しさ
- 近所迷惑が心配になるレベル
- 「抱っこしようか?」「水飲む?」すべて拒否される
- 怒っているようなトーンで30分近く叫び続ける
- 終わるとケロッと寝る(翌朝覚えていないことも)
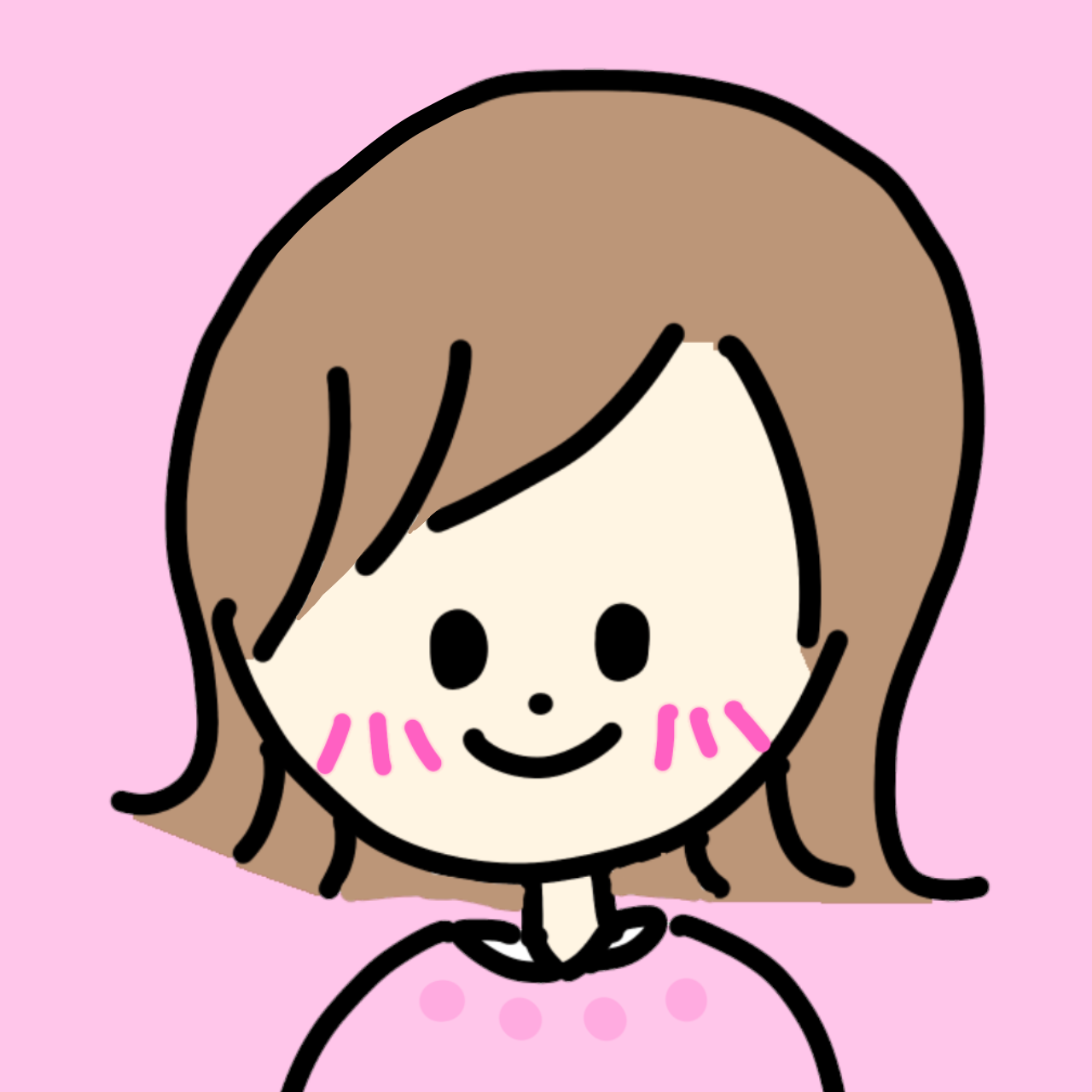
◆ 調べると「夜驚症」?
症状を調べると「夜驚症(やきょうしょう)」にあてはまるように見えました。
ただ、「よくあること」「自然に治る」という説明だけでは、今夜どうすればいいのかの答えにはなりません。
◆ 私の視点:診断名で終わらせない
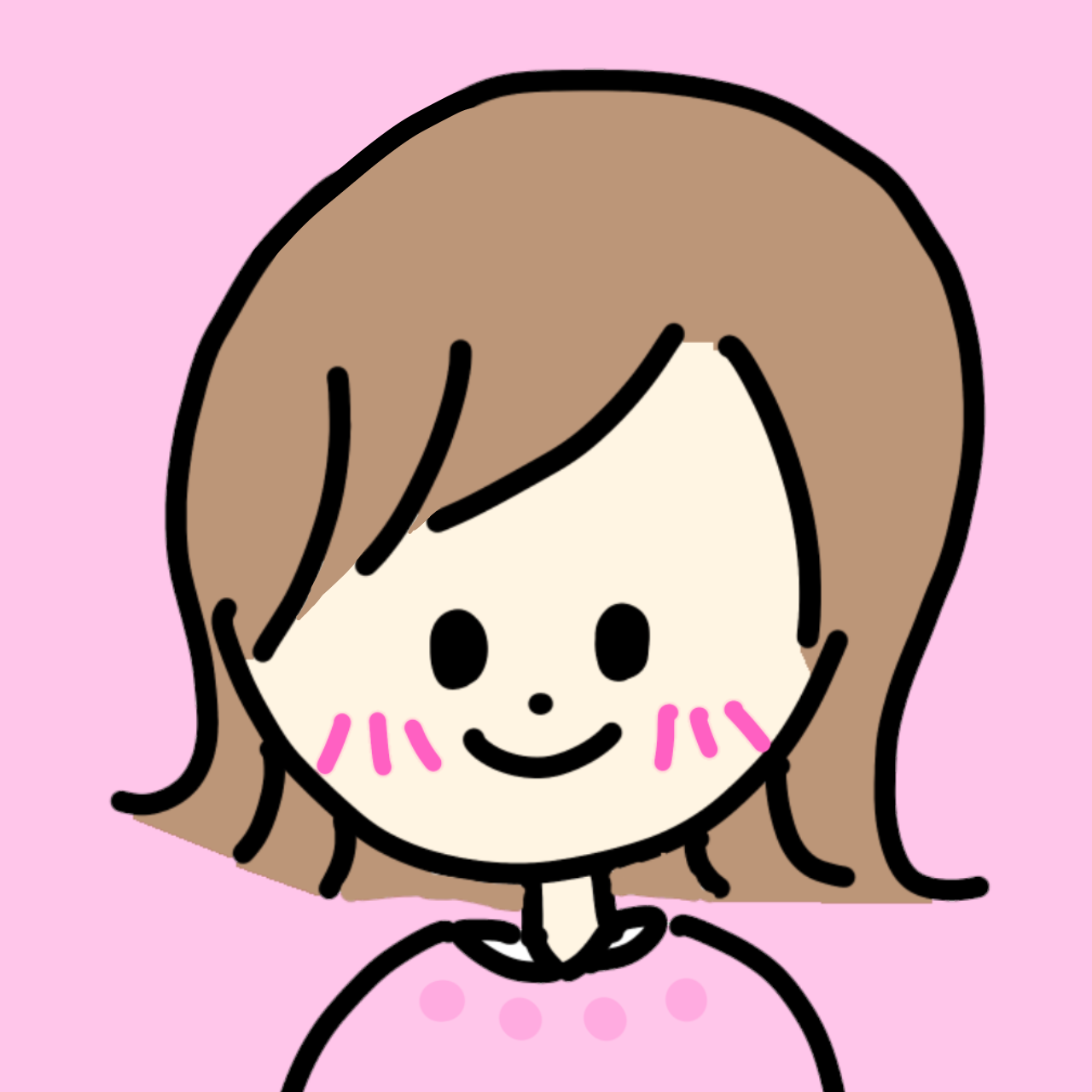
同じ行動でも、原因が違えば対応は変わるからです。
今回も、夜驚症という言葉にとらわれすぎず、「なぜ今、このような泣き方をしているのか?」を見つめました。
◆ 環境の変化を振り返る
- パパが家にいることが増え、子どもと過ごす時間が増えた
- その中で、甘やかし気味の対応が見られた
- ママ(私)は体調不良で関わる時間が減少
- 生活リズムが崩れる日も増えた
- 外遊びが減った、寝つきも悪くなった
◆ はじめは「誤学習」を疑った
泣けばパパにかまってもらえる、という誤学習が強化されたのでは?と考え、最初の対策は「反応しない」こと。
最初は効果があるように見えましたが、解決には繋がりませんでした。
むしろエスカレートしている気がしました。
関連記事:「叱る」とは、信じて待つこと──深夜4時の夜泣きが教えてくれた親の役割
◆ 対策を転換:「愛着行動」として理解し直す
そこで発想を変えました。「夜の泣き叫び」は“試し行動”や“愛着行動”の変化なのでは?と。
つまり、日中の不安が夜間に出ている可能性です。
◆ 対応を変えたら……変化があった
日中、私と子どもが関わる時間を意識的に増やしました。
- 一緒に遊ぶ
- 膝にのせてスキンシップ
- ゆっくり話を聴く
パパにも絵本や散歩を増やしてもらいました。
すると、変化がありました。
泣き叫ぶことがその日は起きなかったのです。
◆ 結論:症状名より「背景理解」が大切
夜驚症という言葉は、確かに参考になります。でも、それだけでは足りません。
「症状には、子どもの何らかの訴えがある」という視点をもつことで、対応が変わり、子どもも安心できます。
◆ このブログで伝えたいこと
私は、育児書の情報をただ「真似る」のではなく、
「子ども自身を見る目」を育てるための視点を届けたいと思っています。
この記事も、私の試行錯誤の記録として、同じように悩む方の参考になれば嬉しいです。
※なお、この記事は医療的診断や専門的助言を提供するものではありません。心配な場合は小児科や専門機関にご相談ください。