教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
執筆時、1歳児自宅保育中
「イヤイヤ期ってこんなに大変なの!?」ストレスMAXのママ・パパへ
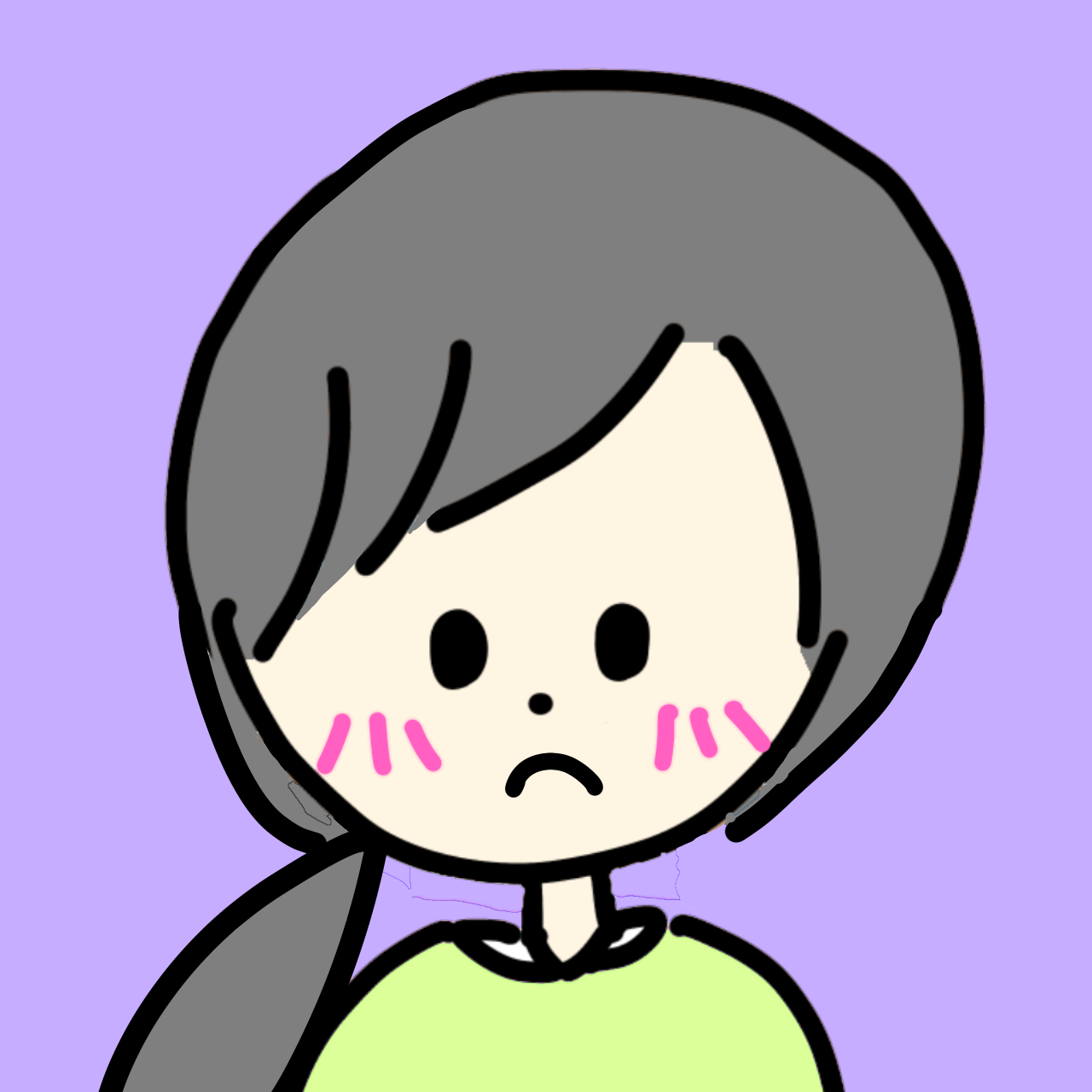
こんなお悩みはありませんか?
✅ 自分の子のイヤイヤ期タイプを知りたい
✅ イヤイヤ期の終わるタイミングが知りたい
✅ 親としてストレスを減らす方法を知りたい
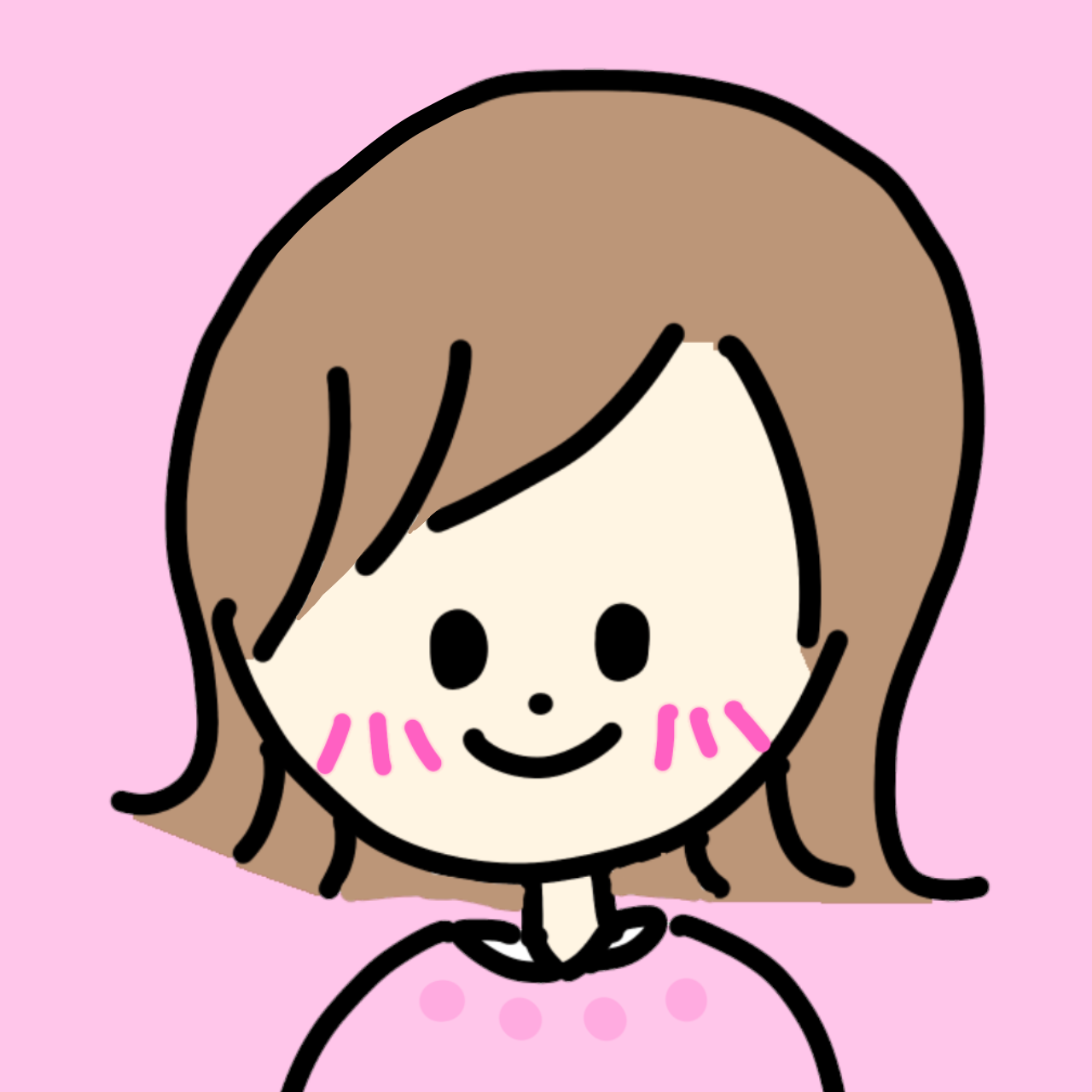
イヤイヤ期とは?いつからいつまで続くの?
イヤイヤ期は1歳半〜3歳頃にかけて訪れる時期で、自己主張が強くなるのが特徴です。
- 1歳半:少しずつ「イヤ!」が増えてくる
- 2歳前後:イヤイヤのピーク(なんでも「イヤ!」)
- 3歳頃:徐々に落ち着くが、こだわりは残る
自分の思い通りにいかない場面で感情が爆発することが多く、親として戸惑うことも少なくありません。
イヤイヤ期の本当の原因とは?
イヤイヤ期は脳の前頭前野の発達で起こるものと考えられています。
例えば、大人は「〇〇してはいけない」と言われたときに、感情を抑えて行動できます。
しかし、幼児の脳は「やりたい!」という欲求を感じる部分が先に発達し、「ダメだ」と抑える部分がまだ未熟な状態。
そのため、「ジュースを飲みたい!」と思っても、大人のように「今はダメだ」と自分で判断するのが難しく、感情が爆発してしまうのです。
脳は感情の部分が先に発達します。一方で、社会的なルールを守るという部分は遅れて発達するので、個人差はありますが多かれ少なかれ、生物学的に反抗期はあるということです。
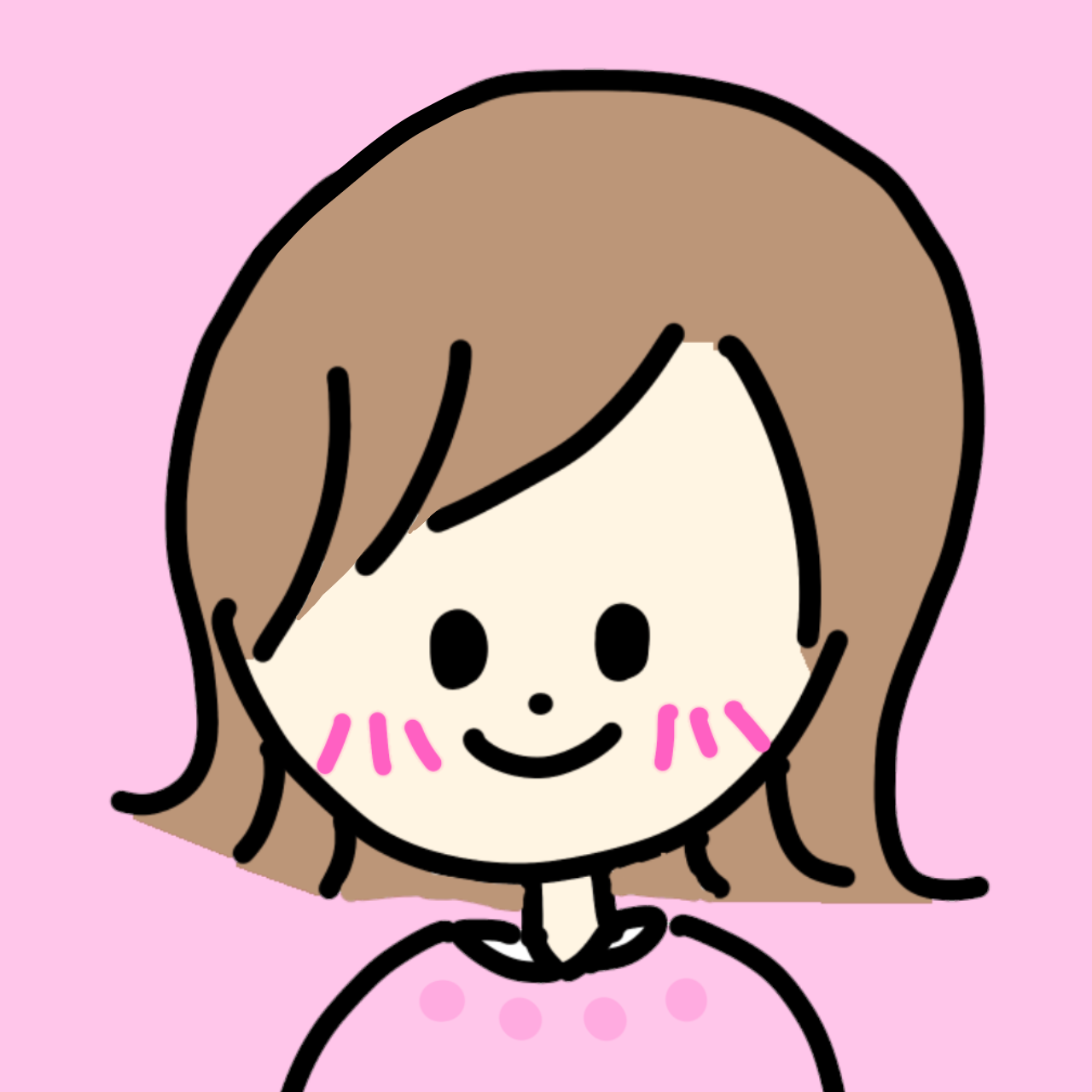
📌 イヤイヤ期タイプ診断【20問】
以下の質問に「はい」または「いいえ」で答え、最後に各タイプの「はい」の数をカウントしてください。
最も多かったタイプが、あなたのお子さんのイヤイヤ傾向です。
⚠️ この診断についてのご注意
-
この診断は医学的・科学的根拠に基づいたものではなく、筆者の経験と知識をもとに作成したものです。
-
お子さんの成長には個人差があり、すべての子どもが当てはまるわけではありません。あくまでも一つの視点としてお楽しみください。
【原因別】イヤイヤ期への対応策
1. 自己主張への対応
✅ 子どもにやらせる余裕がある時
- 失敗してもOKな環境を整える:こぼしてもいいように新聞紙を敷く、スプーンのサイズを変えるなど。
- 部分的に任せる:「ズボンはママが履かせるから、Tシャツは自分で着てみよう」
- 選択肢を与える:「青い靴と赤い靴、どっちにする?」
- 子どもに合わせた環境設定をする:お茶をコップに注ぎたがるなら、小さなピッチャーを用意する(モンテッソーリの考え方)
🚨 余裕がない時の対処法
- お気に入りのアイテムを活用:アンパンマンのパジャマなら着る、電車のお皿なら食べるなど。
- 状況に応じて妥協:パジャマのまま出かけて、後で機嫌が直ったら着替えさせる。
- ポジティブな表現を心がける:「着替えないとダメ」→「お洋服を着ようね」
- 注意をそらす:「この絵は何かな?」と話しかけたり、他の遊びに誘導する。
2. 言葉でうまく表せない時の対応
子どもは自分の気持ちを言葉で整理する力がまだ未発達なため、うまく伝えられずにイヤイヤすることがあります。
- 気持ちを代弁する:「ジュースが飲めなくて悲しかったんだね」
- イラストや絵本で感情表現を学ぶ:気持ちを表す言葉を少しずつ覚える
3. 想像と現実のギャップがある時の対応
「こうなるはず!」と思っていたのに、実際は違っていた時、子どもは混乱してイヤイヤになります。
🛑 イヤイヤを未然に防ぐ対策
- ルーティンを作り、見通しを持たせる:「朝ご飯を食べたら着替える」「お風呂に入ったら寝る」など、行動の順番を固定する。
- 子どもの使うものを固定化:ジュースを飲む時のコップを決める、靴を同じものにするなど。
💡 イヤイヤが始まったら
- トリガーを把握する:子どもが何を想像していたのかを観察し、次回に活かす。
- 共感する:「思っていたのと違ったんだね」
4. 秩序の敏感期への対応
秩序の敏感期の子どもは「いつもと同じ」を求めるため、少しの変化でもイヤイヤにつながります。
✅ 秩序の敏感期の子どもへの対応
- 「いつもと同じ」にできる部分は変えない:「お気に入りのスプーンを用意する」
- 環境を事前に説明する:「今日は違う公園に行くよ」と伝えておく。小さい子でも親の空気感から説明が伝わることがあります。
- 並べる遊びは止めさせない:電車を並べたり、マグネットを整列させる行為は、子どもにとって意味のある行動。
イヤイヤ期はいつ終わる?終わりのサイン
「ずっと続くの?」と心配になるイヤイヤ期ですが、多くの子は3歳半〜4歳頃にかけて落ち着いてきます。
イヤイヤ期の終わりのサイン
- ダメ!」と言われても理由を聞こうとする
- イヤイヤの頻度が減り、自分で折り合いをつけられる
- 物事を「順番」や「ルール」で理解できるようになる
- 秩序へのこだわりが落ち着いてくる
親のストレスを減らす方法
イヤイヤ期は子どもだけでなく、親にとっても大きなストレス源。適切な対策をとることで、負担を減らすことができます。
1. 完璧を求めない
「ちゃんとしなきゃ」と思いすぎると、余計にストレスが溜まります。7割くらいできればOKと考えましょう。
2. イヤイヤ期を「実験」と捉える
「この子はどういうことでイヤイヤするんだろう?」と観察すると、意外と楽しめることも。
3. ひとり時間を確保する
親がリフレッシュする時間を意識的に作ることで、子どもへの接し方にも余裕が生まれます。
4. SNSで他の親の体験談を読む
「自分だけじゃない」と思えるだけで気が楽になることも。
まとめ
イヤイヤ期は、子どもが「自分」を確立するための大切な成長過程です。
本記事のポイント
- イヤイヤ期のピークは2歳前後。3歳半〜4歳で落ち着く
- 「秩序の敏感期」が影響していることを理解する
- 年齢に応じた具体的な対応策を実践する
- 親のストレスを軽減する工夫も大切
この記事を参考に、イヤイヤ期を乗り越えていきましょう!