教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
執筆時、1歳児の自宅保育中
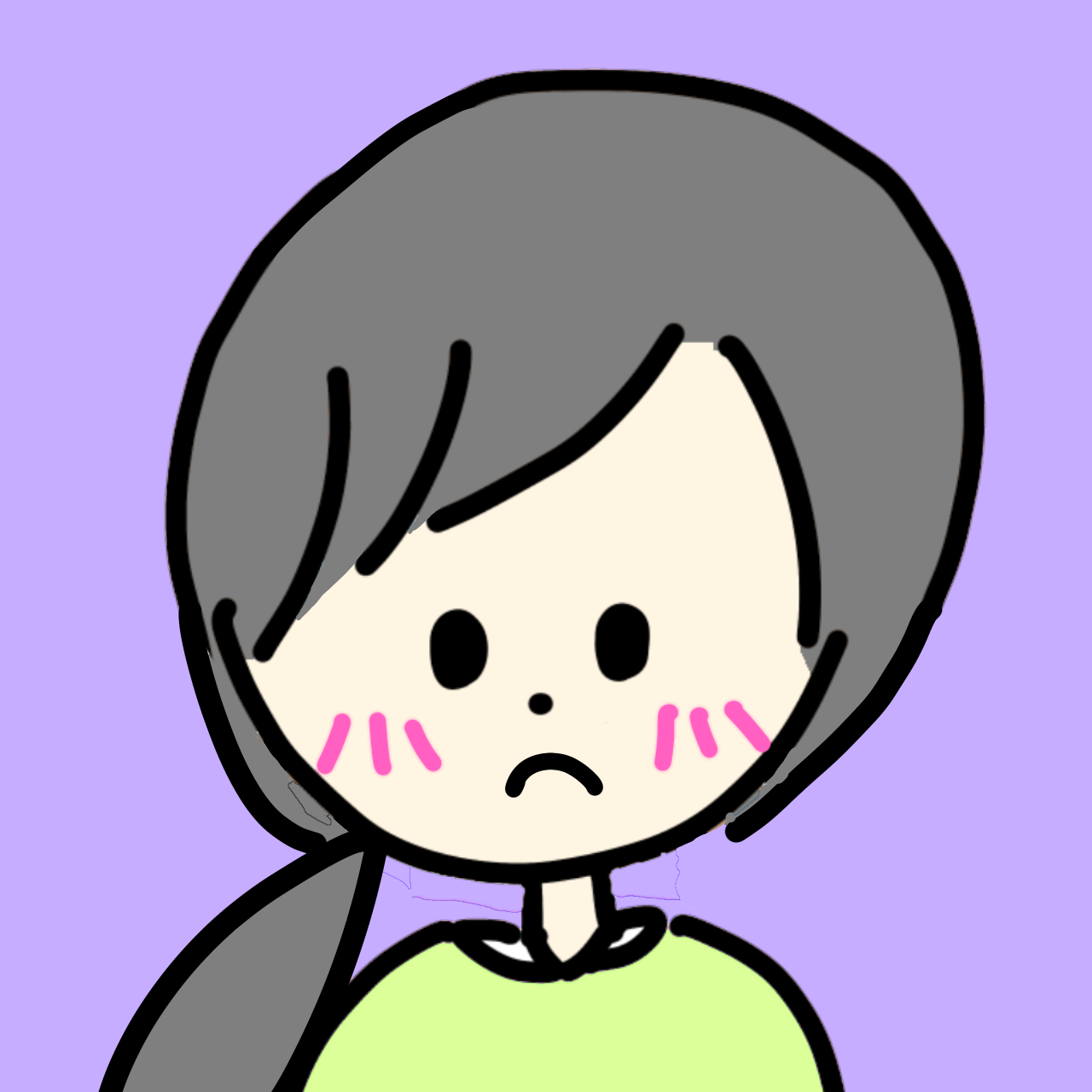
そんなモヤモヤを抱えていませんか?
1. ストレスの原因を見える化して解消する
家事分担の話し合いをするときに、「料理は誰」「洗濯は誰」といった大まかな分け方をしがちですよね。
このやり方だと、自分が苦手なこともやらなければならず、どうしてもストレスが溜まりがちです。
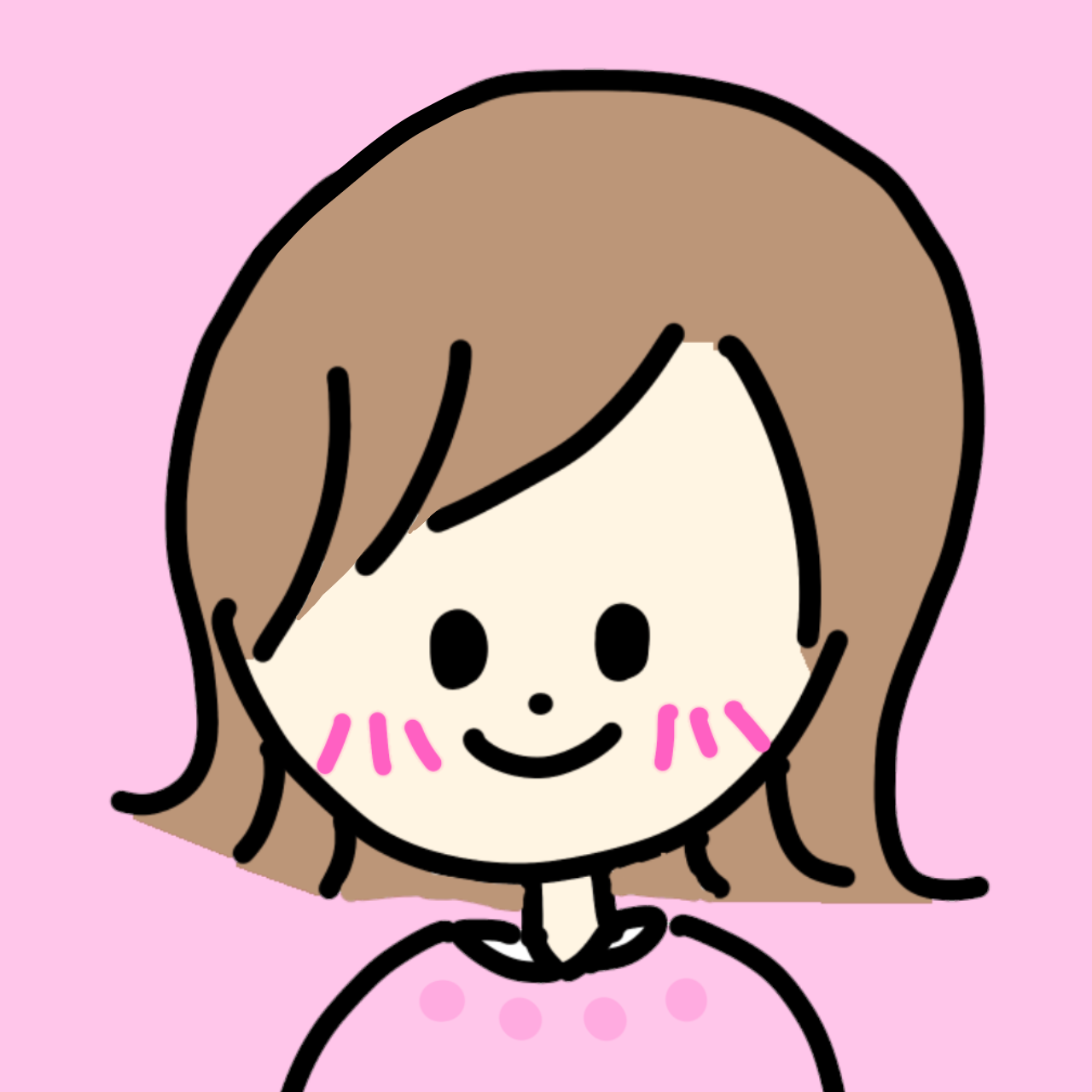
ストレスのポイントを見える化する
私たちの場合、以下のようなストレスが浮かび上がりました。
- 私の場合
- 夫がゴミをまとめた後、袋をしっかりセットしない。
- 子どもと遊んだおもちゃが片付けられていない。
- 料理中に出たゴミがそのまま放置されている。
- 夫の場合
- 私がゴミをまとめてくれない。
- 部屋の隅にゴミが溜まっている。
- 料理の味付けが適当すぎておいしくない。
こうしてお互いの「気になる部分」を可視化してみると、実はそれが自分の得意な部分であることに気づきました。
気になる部分=自分の得意な部分だった!
例えば、私が「ゴミ袋をきちんとセットしてほしい」と感じるのは、自分にとってゴミ袋のセットがそれほど苦ではないからです。
一方で、夫が「料理の味付けが適当」と感じるのも、彼が細かく分量を測るのが得意だからこそ、私の大雑把な味付けが気になるのです。
さらに、夫婦で話し合ってみたところ、それぞれが苦手な部分も見えてきました。
- 夫の苦手なこと
- 手先が不器用で、食材を切るのに時間がかかる。
- 料理中のマルチタスク(炒めながら洗い物をするなど)が苦手。
- 私の苦手なこと
- 味付けを細かく測ることが面倒で、結果的に適当になりがち。
- 細かいゴミまで気にして掃除をせず、大雑把になりがち。
2. 得意を活かす!家事を細分化して割り振る方法
こうした話し合いから、家事を「料理」「洗い物」といった大まかなカテゴリで分けるのではなく、細かく分けて得意な部分を割り振るという方法にたどり着きました。
気になる部分を解消するカギは得意を活かすこと
料理の割り振り
- 妻の担当: 料理の下ごしらえ(食材を切る、下準備をする)、料理中の洗い物
- 夫の担当: 味付け、料理の仕上げ、ゴミ捨て
例えば、私は食材を切ったり、調理中に洗い物を終わらせることにはストレスを感じません。しかし、料理の味付けは面倒で苦手なので、夫に任せています。
ゴミ捨ての割り振り
ゴミ捨ての作業も「まとめる」と「袋を設置する」という2つのステップに細分化しました。
- 私の担当: ゴミ袋を設置する
- 夫の担当: ゴミをまとめて捨てる
私はゴミをまとめる作業が面倒だと感じる一方で、ゴミ袋を設置することは苦ではありません。一方、夫はゴミをまとめる作業には抵抗がなく、このように役割を分けることでお互いの負担が減りました。
家事を細分化してみることで、お互いが得意な部分を担当しやすくなり、結果的に家事全体がスムーズに進むようになりました。
3. 1歳からでもできる!楽しいお手伝いアイデア
小さな子どもでも意外とできることは多く、「できる部分を任せる」ことで、手先の器用さにつながったり、親の負担軽減にもつながります。
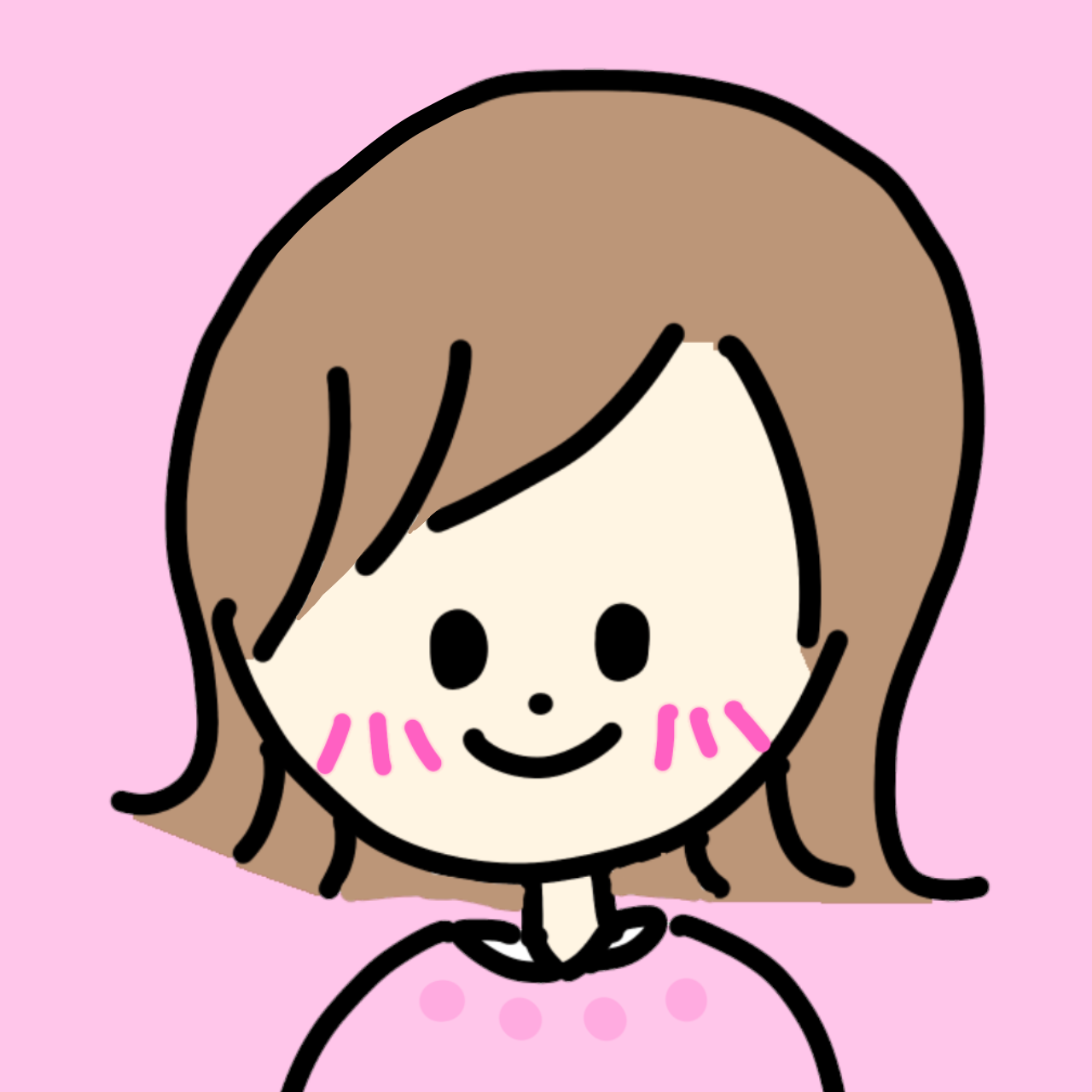
ここでは、我が家で実践している具体的なお手伝いアイデアをご紹介します。
お手伝いの具体例
- 食器を1つずつ運ぶ
- こぼしたお茶をタオルで拭く
- パジャマやクリームを自分で引き出しから出す
- パジャマの袖を通す、クリームをお腹に塗る
我が家のエピソード
我が家の1歳9ヶ月の子どもは、食器を1つずつ運ぶことが大好きです。例えば、「スプーンを持ってきてね」と言うと、スプーンを持ってきて、次にフォークを運び、お皿、コップと順番に運んできます。
大人からすると効率が悪く見えるかもしれませんが、子どもにとっては楽しい遊びのようなもの。歩きながら運ぶのが楽しいらしく、何往復もしてくれるので、その間に私は食器洗いを終わらせることができて助かっています。
また、こぼしたお茶を拭くといった簡単なことも、自分でタオルを使って完結できるようにしています。時にはティッシュで拭き、ゴミ箱に自分で捨てることもできるようになりました。
任せるコツ
- 「できる部分をやらせる」ことに重点を置く。
- 例えばおむつを履く場合、子どもが引っ張れるところまで自分でやらせ、最後の難しい部分を少し手伝う。
- 子どもの手の届く場所に必要なものを配置して、自分で選んだり取り出したりできる環境を作る。
褒めて伸ばす環境作り
子どもが自分で何かを達成した時には、「ありがとう」「すごいね」と声をかけ、成功体験を積ませましょう。
褒められることで、子どもはさらに進んでお手伝いをしたくなり、自立心が育ちます。
効率化のポイント
子どものお手伝いを活用することで、育児と家事を効率化できます。たとえば、食器を運んでもらっている間に洗い物を進めたり、お風呂上がりにスキンケアをしている間にクリームを取り出してもらうことで、少しの時間を有効活用できます。
また、幼い子どもに任せるのは大変だと思われるかもしれませんが、実はできるようになった中高生に任せる方が難しいことも少なくありません。
中高生になると手伝いは面倒臭い、他にやりたいことがあるなどで結局やらないことが多いためです。
小さい子の場合、初めは失敗もありますが、できるようになるのも意外と早く、お手伝いを楽しむ気持ちを持っています。今のうちにお手伝いを習慣化させた方が将来的にも楽になります。
4. まとめ:夫婦と子どもの「特性」を理解して家事をもっと楽に!
■役割分担と得意分野の考慮
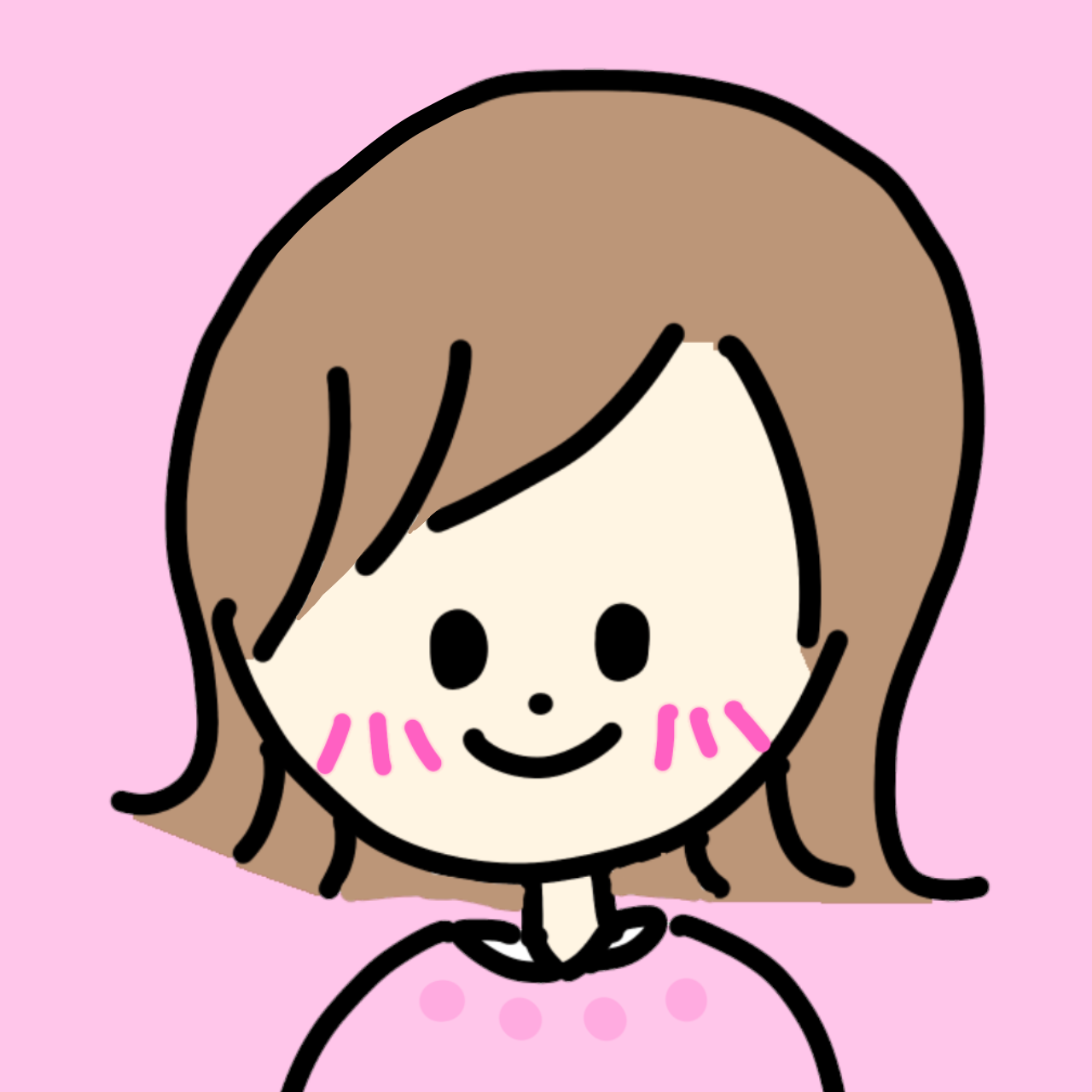
この視点を持つことで、イライラの原因が特性の違いにあることが分かるようになりました。
私自身、特別支援の知識から学んだのは、人には得意な部分と苦手な部分が必ずあるということです。夫と私でも、考え方や行動の特性は異なり、それぞれの強みを活かすことで家事分担がスムーズに進むことに気づきました。
■家族の仕組みと協力の重要性
ヒトはもともと集団で生きる生物です。本来、多くの大人が集団となり、で複数の子どもを育てる生物ですが、現代では2人で子どもを育てるのが一般的で、負担が集中しがちです。
そのため、うまくいかないのは当たり前だと考え、できるだけ外部の助けを借りたり、家族全体で協力し合うことを意識しています。
家事や育児を完璧にこなそうとせず、家族全体で役割を分担し、心地よい仕組みを作ることが最優先だと感じます。
■おわりに
家事の分担で重要なのは、それぞれの得意な部分を活かして分担することです。また、子どもにも少しずつ家事を任せることで、育児と家事の効率化が実現し、子どもの成長もサポートできます。
完璧を求めすぎず、家族全体で支え合う仕組みを作り、楽しく快適な日常を目指してみませんか?