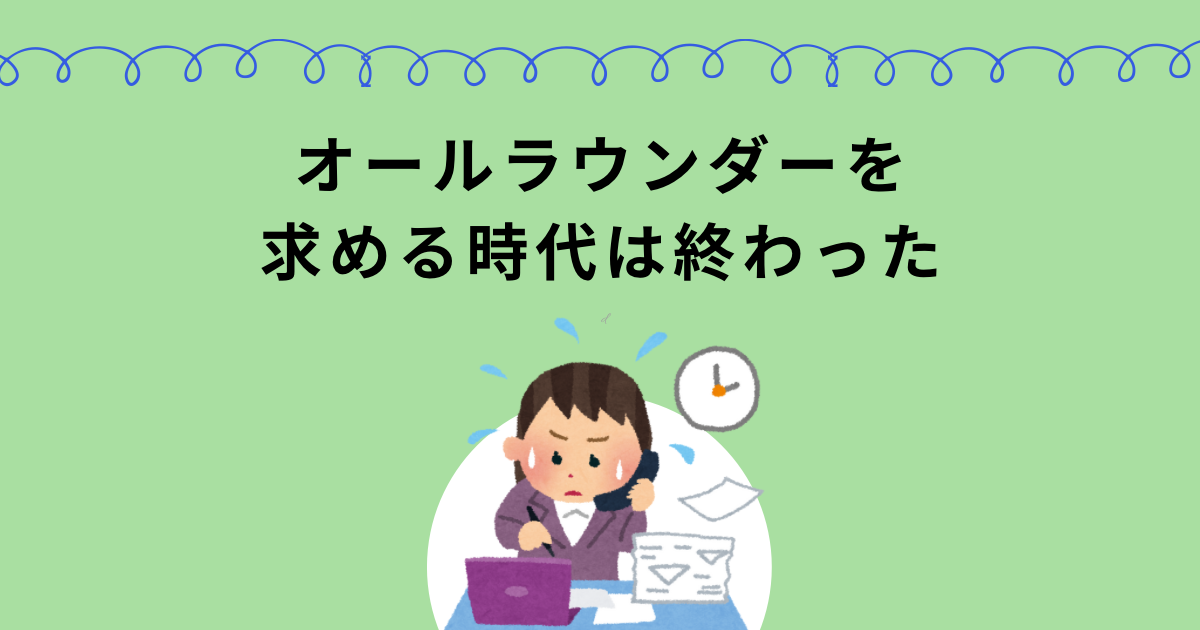教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
特例子会社へのアドバイス経験あり
「この人なら全部任せられる」「あの人は何でもできて助かる」──そんな“オールラウンダー”に支えられてきた職場ほど、いつの間にかその人が燃え尽きて辞めてしまう。採用やマネジメントの現場で、そんな経験はありませんか?
1. オールラウンダーを求めすぎる職場の限界
多くの職場で、「何でもできる人」が理想とされがちです。
採用の現場でも「柔軟に対応できる人」「即戦力」「コミュニケーション能力が高い人」など、幅広いスキルを求める傾向があります。
たしかに、限られた人員で業務を回す必要がある中で、マルチに動ける人材は貴重です。
しかし、現場でのマネジメントに目を向けると、次のような課題が浮き彫りになってきます。
- ひとりの社員に多くを求めすぎて、負担が偏る
- 苦手な業務にストレスを抱え、モチベーションが下がる
- 得意を活かせない配置でパフォーマンスが発揮されない
- 新人や多様な人材が定着しづらくなる
このような状態が続くと、結果として「人が育たない」「人が離れる」職場になりやすくなります。
その背景にあるのが、「オールラウンダーであること=優秀」という前提です。
しかし本当に、すべての人が「何でもそつなくこなせる」ことを目指すべきなのでしょうか?
実際のところ、人にはそれぞれ「得意なこと」と「苦手なこと」があります。
にもかかわらず、「できない部分」に注目して改善させようとする文化は、結果的に社員の自信ややる気を削ぐ要因になります。
重要なのは、「万能であること」よりも、「自分の強みを発揮できるポジションにいること」。
それが、結果としてチーム全体の力を底上げすることにつながります。
この章では、まず「オールラウンダー主義」の限界を明らかにし、次章からは業務や職場の構造そのものを「特性ベース」で見直す視点を提案していきます。
2. 業務は実は多様な認知特性の組み合わせ
日々の仕事は「単純な作業の連続」に見えるかもしれません。
しかし、その一つひとつを分解してみると、実は驚くほど多くの能力・特性が必要とされていることに気づきます。
たとえば、飲食店でオーダーを取る仕事を考えてみましょう。
一見単純な業務に見えても、そこには以下のようなスキルが求められています。
- メニューを覚える「記憶力」
- お客様の注文を正確に聞き取る「聴覚処理力」
- 混雑時に優先順位を判断する「状況判断力」
- 笑顔で接客し続ける「感情表出力」
このように、たった1つの業務でも「複数の認知特性」が重なり合って構成されています。
つまり、業務とは「単体のスキル」ではなく、「さまざまな特性の集合体」なのです。
これはオフィス業務でも同様です。たとえば、事務職の「データ入力」という業務ひとつとっても、
- ミスなく作業を続ける「集中力」
- 同じ作業を繰り返す「持続力」
- 数字や文字を見分ける「視覚認知力」
こうした能力が自然に求められています。
「当たり前の仕事」を「当たり前にこなす」ためには、じつは多くの脳の処理力が必要なのです。
だからこそ──「不得意」は責められるものではない
ここで重要なのは、「仕事ができる/できない」は単なる能力の有無ではなく、
「その仕事に必要な特性と、その人の特性が合っているか」という視点で見直すことです。
特定の業務が苦手でも、それは「能力が低いから」ではなく、
「その業務に必要な特性」と「その人の特性」が合っていないだけかもしれません。
言い換えれば、適切な特性が求められる場に配置されれば、誰もが力を発揮できる可能性があるということです。
次章では、こうした「特性ベースの視点」で業務をどう見直すか──
具体的に「できる・できない」を特性単位で分けて考える方法をご紹介します。
こちらもCHECK
-
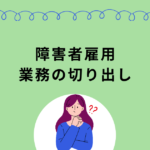
-
任せる仕事がない?障害者雇用で「社内ニート」が起きる理由と業務の切り出し方
続きを見る
3. 「できる・できない」を業務単位でなく、特性単位で分けてみる
一般的に、仕事の現場では「この仕事ができるか/できないか」で人を評価しがちです。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
たとえば「事務作業ができるか?」と一括りにされると、苦手な部分があっただけで「この人は事務ができない」と評価されてしまうことがあります。
ですが、実際にはこうです。
- データ入力の正確さ → 高い
- スケジュール管理 → 苦手
- 対人調整(電話・メール)→ 得意
このように、「事務作業」と言っても、中に含まれているスキルや特性はバラバラです。
業務を細かく分解してみる
そこで必要なのが、「業務を細かく分解して考える視点」です。
業務単位で見るのではなく、次のような単位で分けてみましょう。
| 業務項目 | 必要な特性 |
|---|---|
| データ入力 | 集中力、視覚認知、単純作業持続力 |
| スケジュール調整 | 情報整理力、全体把握力、対人交渉力 |
| 資料作成 | 文章構成力、注意深さ、タイムマネジメント |
こうして特性単位に分けると、
「この部分はできるけど、あの部分は苦手」という構造が見えてきます。
苦手を無理に埋めさせない
この視点を持つと、無理にすべての業務をひとりに押し付ける必要がないことに気づきます。
- データ入力が得意な人には、集中して打ち込むタスクを。
- 対人調整が得意な人には、顧客対応やチーム調整を。
それぞれの「得意」が生きる配置を意識することで、
チーム全体の生産性も、メンバーの満足度も、大きく向上させることができるのです。
特性を活かす職場設計が、離職を防ぐ
「できない部分」にばかり目を向けて修正しようとすると、
本人は疲弊し、自信を失い、最終的には職場を離れる選択をするかもしれません。
逆に、特性を活かした配置・分担ができていれば、
多少の不得意があっても、「このチームで働き続けたい」と思える環境を作れます。
次章では、この「特性ベースの職場設計」が実際に実践されている好事例として、
障害者雇用の成功例である「久遠チョコレート」の取り組みをご紹介します。
4. 久遠チョコレートの実例──特性を活かす職場設計とは?
「特性ベースの職務設計」は理想論に聞こえるかもしれません。
しかし、実際にこの考え方を現場で形にしている企業があります。
それが、障害者雇用にも力を入れている「久遠チョコレート」です
久遠チョコレートとは?
久遠チョコレートは、全国に店舗を展開するチョコレートブランド。
特徴は、高品質なチョコレートづくりを通して、障害者・高齢者・多様な人材が働き手として活躍できる職場をつくっていることです。
ここでは「障害があるから配慮する」のではなく、その人の特性を理解し、活かせる作業工程を設計することに力を入れています。
久遠チョコレートで実践されている工夫
- 作業工程を細分化:チョコレート作りに必要な作業を、さらに小さな単位に分解。
- 個々の特性に合わせた配置:「集中力が高い」「細かい作業が得意」「短時間なら力を発揮できる」などを考慮して役割分担。
- 工程を「見える化」:視覚的に手順を示すことで、認知特性の違いをカバー。
- 段階的なステップアップ:得意な作業から始めて、少しずつ業務範囲を広げていく。
つまり、「できることに合わせて作業を設計」しており、
逆に「できないことを無理にさせない」仕組みになっているのです。
成果として現れていること
この仕組みがあることで、久遠チョコレートでは次のような成果が生まれています。
- 障害の有無にかかわらず、一人ひとりが自信を持って働ける。
- 無理な負担がないため、離職率が低い。
- 工程を分担しても、製品の品質が非常に高い。
- 「多様な人材が働いている」という企業ブランディングにもつながっている。
なぜうまくいくのか?
久遠チョコレートの成功要因はシンプルです。
- 「オールラウンダーを育てる」のではなく、「一人ひとりの強みを引き出す」発想。
- 業務の構造(工程・役割分担)自体を、人に合わせて柔軟に設計した。
つまり、「人を枠に合わせる」のではなく、「枠を人に合わせる」ことで、自然と人材の力が引き出されているのです。
この発想は、障害者雇用だけではなく、あらゆる企業の組織設計・マネジメントに応用できる非常に重要なヒントになるでしょう。
次章では、さらに実践的な視点として、どのように特性ベースで職務を再設計していくかを詳しく掘り下げていきます。
5. 特性ベースの職務再設計──「できる」を最大化する組織のつくり方
久遠チョコレートの例で見たように、特性ベースで職場を組み立てると、無理なく人材の力を引き出すことができます。
ここからは、自社でも実践できる「特性ベースの職務再設計」について、ステップごとに解説していきます。
ステップ1:業務を「機能単位」に分解する
まず、現在の業務内容を「大きな仕事のかたまり」として捉えるのではなく、もっと細かく「機能」ごとに分解していきます。
例:営業職の場合
- 新規顧客リストの作成(リサーチ・リストアップ)
- テレアポ(電話でアポイントを取る)
- 訪問・提案活動
- 契約書類の作成・処理
- 顧客管理システムへの入力・更新
このように、「営業」という大きな括りではなく、実際に発生している作業を細かく分類します。
ポイントは「作業内容」と「必要な特性」を分けて捉えることです。
ステップ2:「必要な特性」を洗い出す
次に、各機能(作業)を行う上で必要な特性を洗い出していきます。
例:
- リサーチ→集中力・正確さ・検索力
- テレアポ→瞬発力・対人ストレス耐性・簡潔な伝達力
- 訪問・提案→臨機応変さ・共感力・説得力
- 契約書類作成→慎重さ・細かい作業への耐性・ミス防止力
- データ入力→継続的な集中力・作業の単調さに耐えられる力
このように作業別に「向き・不向きの特性」を整理すると、
一人に全部を求める設計そのものに無理があったことが見えてきます。
ステップ3:「特性マッチング」を考える
各作業ごとに、誰が一番「無理なく、自然体でできるか」を考えます。
ここで重要なのは、「苦手を克服させようとしない」ことです。
苦手なことを頑張らせるより、得意な特性を活かして「強い部分を伸ばす」方が、生産性もモチベーションも格段に上がります。
ステップ4:「役割」を再設計する
特性マッチングができたら、それをもとに新しい「役割分担」を設計します。
- リサーチとデータ入力をメインに担当する人
- 訪問・提案活動を得意とする人
- 契約関連や事務作業を得意とする人
このように、従来の「職種」ベースではなく、「特性」ベースで業務を組み直すイメージです。
ステップ5:定期的に見直す
人の成長や組織の変化に合わせて、定期的に「業務と特性のマッチング」を見直しましょう。
一度組んだら終わりではなく、柔軟に再調整できる体制をつくることがポイントです。
特性ベース設計のメリットまとめ
- 離職率の低下:無理な業務負荷が減るため。
- 生産性の向上:得意分野で力を発揮できるため。
- 多様な人材の活躍:今まで埋もれていた力を活かせる。
- 組織の柔軟性向上:変化に強いチームになる。
つまり、特性ベースの職務設計は「人材育成」でもあり、「組織戦略」そのものだということです。
次章では、さらに具体的に、自社で特性ベースの業務設計を実践するためのチェックリストをご紹介していきます!
6. 自社で特性ベースの業務設計を考えるためのチェックリスト
特性に合わせた仕事の組み立てを、自分たちの組織でも考えてみるために。
まずは、現状を振り返るところから始めてみませんか?
以下の項目に、一つずつ向き合ってみてください。
1. 業務内容の見える化
□ 業務をタスク単位に分解できているか?
□ その業務に求められる「特性」(記憶力、集中力、判断力など)は何か?
□ 一人の担当者が担っている業務の中に、異なるタイプの特性が混在していないか?
2. 個人特性の把握
□ 社員一人ひとりの得意・不得意を把握できているか?
□ 本人の特性に合った業務アサインを意識できているか?
□ 苦手なことを「努力で克服させる」前提になっていないか?
3. 切り出しと再設計の工夫
□ 業務を「できることベース」で切り出して考えたことがあるか?
□ 工程ごとに分けて「リレー式」に業務をつなぐ発想を持てているか?
□ 手順やルールを整理・標準化し、特性に応じた対応ができる準備はできているか?
4. 組織体制・運営の工夫
□ 分担によって単純作業化しすぎない工夫(達成感・成長感)を意識できているか?
□ チーム単位で成果を見る文化をつくれているか?
□ 障害のある社員も、ない社員も、役割分担の意義を共有できているか?
5. 外部支援の活用
□ ジョブコーチや専門機関など、外部の知見を取り入れる準備ができているか?
□ 必要に応じて社内研修や理解促進の取り組みを計画できるか?
7. これからの採用・育成・マネジメント
ここまで、特性ベースの職場設計について解説してきました。
では、これからの時代に適応するために、採用・育成・マネジメントはどう変わるべきなのでしょうか?
この章では、特性ベースを前提とした新しい人材戦略について提案していきます。
1. 採用:万能型ではなく「特化型」のポテンシャルを見抜く
これからの採用では、「なんでも平均点」より「特定領域で強みを持つ」人材を見極める視点が必要です。
- 汎用的スキルだけでなく、尖った強みを評価する
- 本人が自然体で発揮できる力に注目する
- 「この業務にはこの特性がハマる」というマッチングを意識する
例えば、営業職でも「商談力が高い人」と「細やかな関係構築が得意な人」は異なる特性を持っています。
同じ枠組みで比べず、どのフィールドで力を発揮できるかを見極めましょう。
2. 育成:「苦手克服型」から「強み伸長型」へ
従来の育成は「できないことをできるようにする」アプローチが主流でした。
しかし、これからは「得意なことを最大化する」育成が主流になります。
- 全員に「オールラウンダー化」を求めない
- 強みを伸ばして専門性を高める
- 苦手な分野は、他者との協力やツールで補完する
苦手を責める文化ではなく、お互いの特性を尊重し、支え合う文化へ。
これが組織の心理的安全性とパフォーマンスを同時に高めます。
3. マネジメント:「結果主義」だけでなく「適材適所主義」へ
マネジメントも、大きくシフトする必要があります。
- 結果だけで評価するのではなく、プロセスや適材適所への配慮を評価する
- 目標設定も「一律基準」ではなく「個別基準」を取り入れる
- 特性に合った業務設計を、マネジメントの役割と位置付ける
マネージャーに求められるのは、単なる「業績管理者」ではなく、
「強みを引き出すプロデューサー」への進化です。
まとめ:特性を起点に「組織のパズル」を組み直そう
これからの採用・育成・マネジメントで目指すべきは、
「万能型の完璧な個人」を探すのではなく、
「違う特性を持つ人同士がパズルのようにかみ合う組織」をつくることです。
一人ひとりの特性を尊重し、活かし合う。
その結果、個人も組織も無理なく、最大限の力を発揮できる。
そんな新しい働き方を目指していきましょう。
関連記事
知らないと損する。障害者雇用を成功させるなら業務の切り出しを徹底せよ