教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
執筆時、1歳児自宅保育中
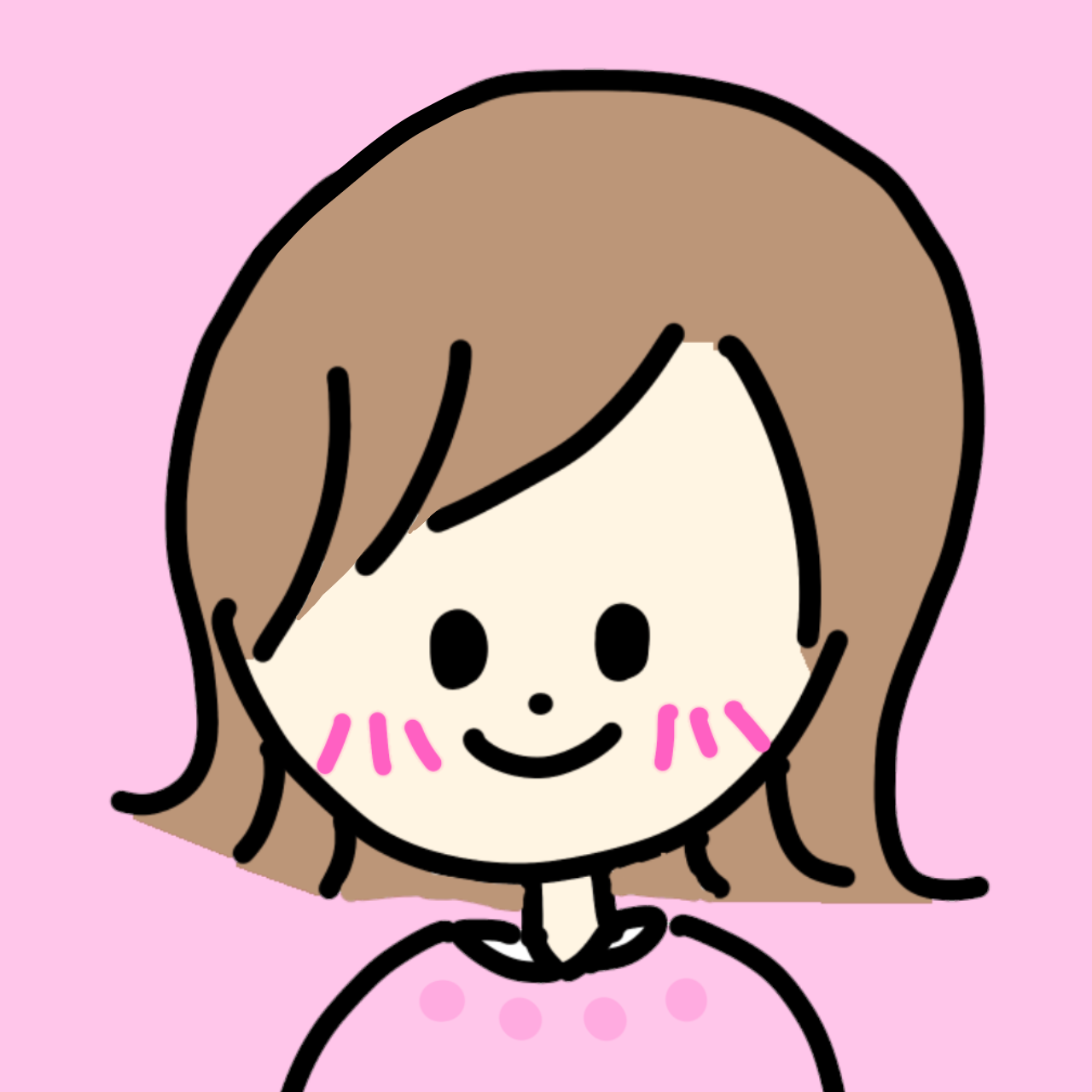
この記事の内容
この記事について
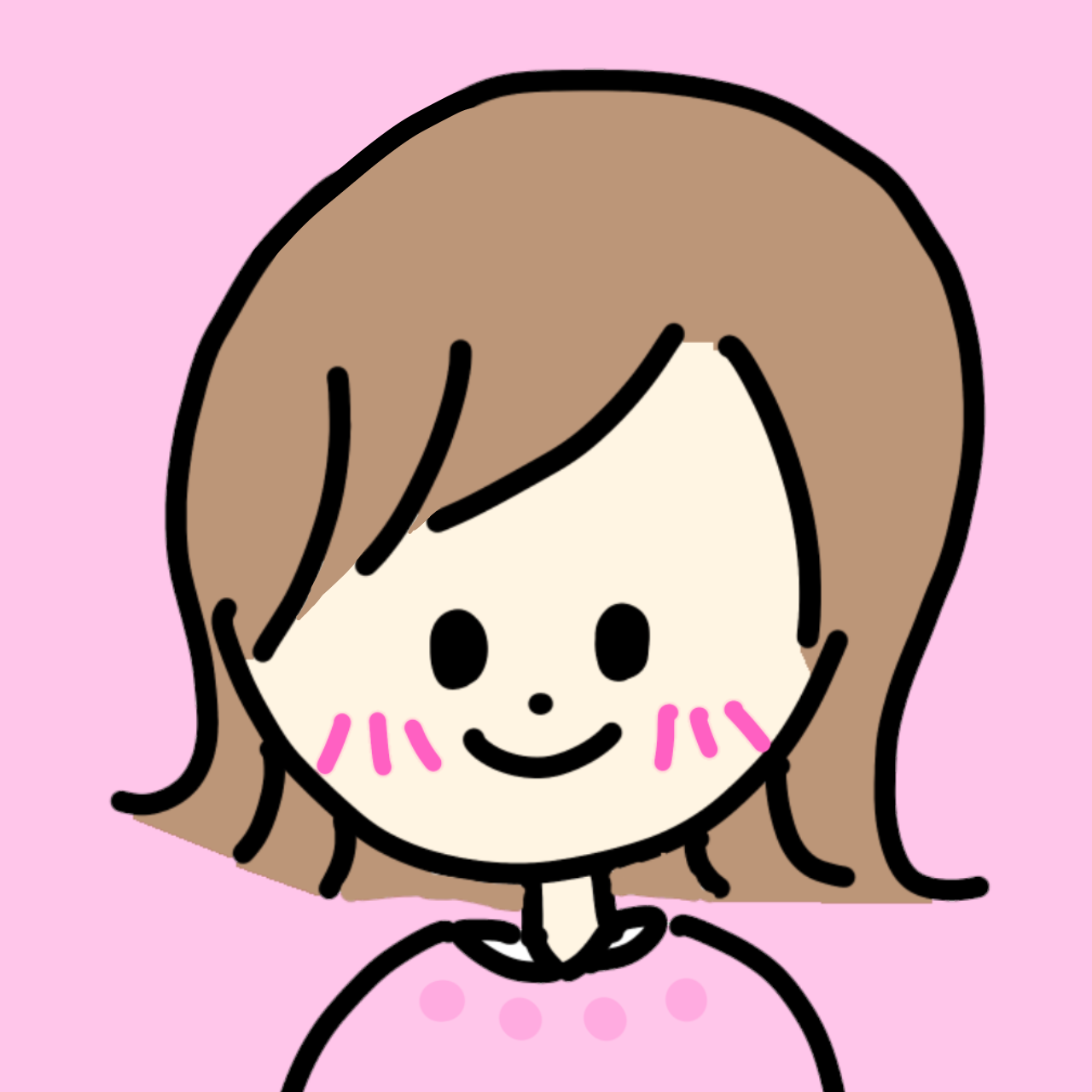
1. 学びの途中段階の内容が含まれています
2.情報の正確性や完全性が保証されていない場合があります
1. 発達の過程における共通点とは?
子どもが成長する過程では、定型発達の子どもも障害を持つ子どもも、それぞれのペースで「発達のステップ」を踏んでいきます。
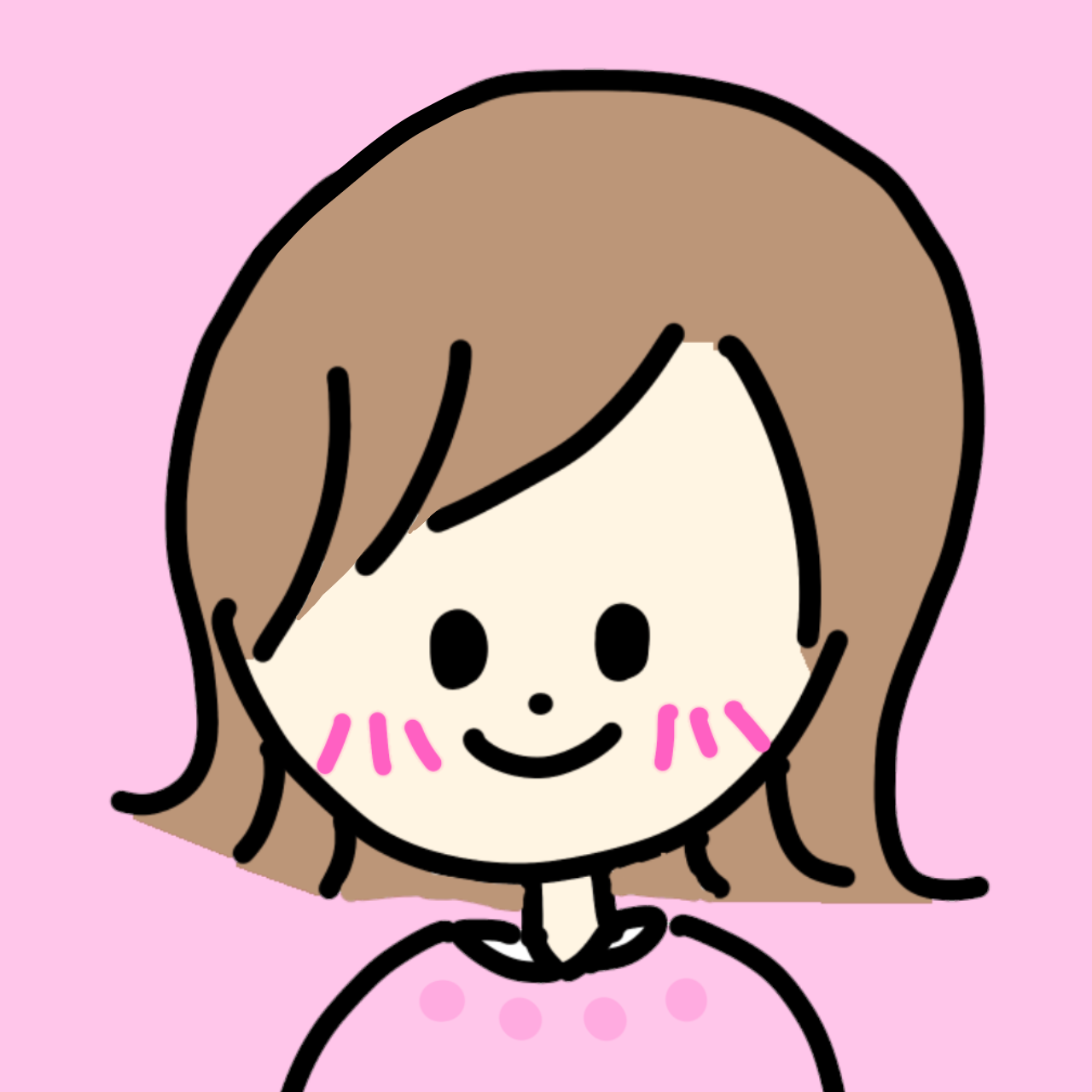
たとえば、秩序に対するこだわりや、ルールが崩れると感情が爆発するような行動は、どちらの子どもにも見られるものです。
違いがあるとすれば、それが「いつ」「どのくらいの期間続くか」という点なのです。
2. 具体的なエピソード:秩序へのこだわり
秩序の敏感期と子どもの行動
執筆時、私の子どもは1歳9ヶ月。モンテッソーリ教育で「秩序の敏感期」と呼ばれる時期がきたように感じています。
この時期には、物事の順番やルールなどに対して非常に強いこだわりを持つことがあります。
関連記事:【元教員が解説】イヤイヤ期の特徴と具体的対応法!秩序の敏感期を理解してストレス軽減
具体例:パンをめぐる秩序の敏感期
ある朝、うちの子にパンを袋ごと出していたところ、「全部少しずつかじりたい」という行動を見せました。
そこで、夫がパンを取り上げた途端、大泣きに…。
これは「すべてのパンを一口ずつ食べる」という秩序が崩れたことへの反応だったのかもしれません。
このような行動には敏感期特有の秩序感が影響していると感じます。
自閉症児の特徴との共通点
一方で、自閉症の子どもたちも同じように秩序にこだわる傾向が見られます。
たとえば、「学校中のドアを閉めながら移動する」「いつもと順番が違うとパニックになる」といった行動を示すことがあります。
3. 障害を「量的な違い」として捉える視点
私が考えるのは、障害がある人とない人で、質的な違いがあるわけではないということです。
定型発達の子どもたちも持つ「こだわり」や「困りごと」が、障害を持つ子どもたちにはより強く、長く表れるだけではないでしょうか。
秩序を守ることに強いこだわりを持つ子どもたちは、成長の過程で秩序を守ることが必要であり、また、それが生活を安定させるための方法として表れているとも考えられます。
4. 親や教育者ができること:環境とサポートの工夫
1. 環境を子どもに合わせる
子どものこだわりを無理にやめさせるのではなく、周囲の環境を子どもに寄り添う形に変えてみるのはどうでしょうか。
たとえば、ドアが気になる子どもには、「ドアを閉める役割」を任せると安心して過ごせることがあります。
2. 行動の背景を理解する
どんな行動にも理由があります。
「なぜこの行動をするのか?」「どんな時に起きるのか?」という視点を持つことで、子どものニーズや気持ちが見えてくることがあります。
3. 長い目で見守る
障害の有無に関係なく、成長にはそれぞれのペースがあります。
「この行動はいつか終わるもの」と捉え、無理に直そうとせずに成長を見守ることも大切です。
5. まとめ:子どもの成長に寄り添う
定型発達の子どもと障害を持つ子どもには、多くの共通点があります。その行動は「異質なもの」ではなく、成長の一部であり、安心感を得るための大切な方法なのです。
親や教育者がその行動の背景を理解し、無理に直そうとせずに寄り添うことで、子どもたちはより安心して成長することができます。