※アフェリエイトを利用しています
教員歴6年の元教員が執筆
関わってきた子どもの数述べ300人以上
自宅保育中
この記事で伝えたいこと
- 2歳でも“教えなくても学べる”瞬間がある
- 子どもが好きなテーマを多角的に学ぶ方法
- 学びを『教える』から『仕込む』へ。
- 家庭でできる「日常の学びの種まき」アイデア
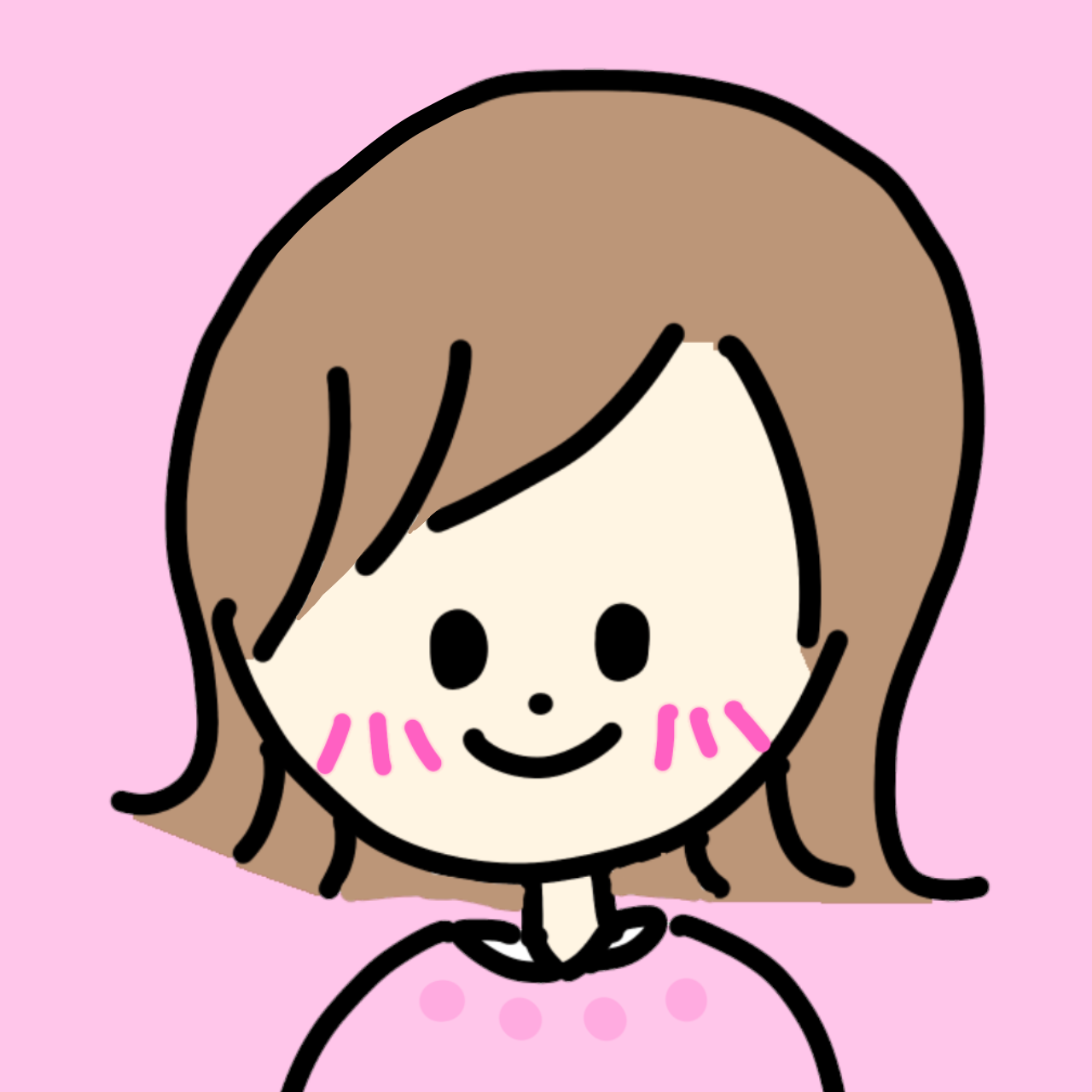
日常の中で静かに始まっているのかもしれません。
ポイント
絵本や歌、遊びを通じて、“学びの芽”を育てています。
好きなものから始まる「学びの芽」
「ねないこだれだ」を読んで以来、おばけが大好きになりました。
まるで物語の世界に入り込むように楽しんでいます。
「おばけ漢字えほん」との出会い
そんな中で出会ったのが『おばけ漢字えほん』。まだ2歳なので漢字が読めるわけではありません。
でも、“おばけ”という親しみのあるテーマで絵本を楽しんでいます。
このような「なにげなく触れた記憶」が、
将来、小学校で漢字を習ったときに「知ってる!」という感覚に
つながるのではないかと思うのです。
絵本だけじゃない:多角的なアプローチ
絵本・言葉・想像力
『ねないこだれだ』などの繰り返し絵本で、物語理解・音のリズムを吸収
ごっこ遊びで空間認識や想像力を育てる
音楽・身体表現
『おばけなんてないさ』を一緒に歌って、音感・発音・抑揚を楽しむ
YouTubeで英語の歌を見て、自然に英語耳が育つ
https://youtu.be/rHtq5GIIUV8?feature=shared
工作・自己表現
おばけを描く・作ることで、想像を形にする力を身につける
文字・記号との出会い
『おばけ漢字えほん』で「まだ読めないけど“知ってる!”」感覚を育てる
これが将来の漢字学習につながる“布石”になるかもしれません
ポイント
「好きなことを深めていたら、結果的に学んでいた」という感覚を味わえるように、遊びの中に学びを仕込んでいます。
日常に“仕込む”学びとは?
何か特別な教材を買ったり、難しい指導をする必要はありません。
ポイント
- 子どもの“好き”を起点に
- 絵本・歌・遊びを“多角的に”展開し
- 日常の中に自然と“種まき”をしておく
子どもは興味のあることには驚くほど集中し、自分で吸収していきます。
年齢×内容レベルで分類した おばけ絵本リスト
※年齢はあくまで目安です。
子どもによって発達や興味の持ち方には大きな個人差があります。
「好き」や「くり返し読む力」を大切に、お子さんに合う本を選んでいただけたらと思います。
【1〜2歳ごろに親しみやすい絵本】
言葉が少なく、繰り返し表現・シンプルな構成・絵の力で楽しめる絵本たち。初めてのおばけ絵本にぴったり。
- 『ねないこだれだ』(せなけいこ)
── 夜更かしするとおばけに連れていかれる!?リズム感が心地よく、定番の1冊
- 『おばけがぞろぞろ』(ささきまき)
── いろんなおばけが登場する楽しい構成。ストーリーというより列挙型でわかりやすい
【1歳半〜2歳半/くり返し読む中で理解が深まる絵本】
ストーリーはあるが短め。発語ややりとりが増えた頃におすすめ。言葉・感情の理解を助ける内容。
- 『こわくないこわくない』(内田麟太郎/大島妙子)
── 何を言われても反対のことを言う、まーくんのお話です
- 『みてみておばけ』(ささき みお)
── 障子にうつった影がおばけに見える「みてみて何かな?」と想像力が広がる絵本です
- 『オバケ!ホント?』(岡田 善敬)
── 子どもたちの身の回りにある何の変哲もない物が、白い布をかけて目を付けるとオバケに変わります。
【2歳半〜4歳ごろ/物語理解と想像が広がる絵本】
ストーリー展開やキャラクター性がある絵本。登場人物の気持ちを想像したり、生活や習慣と結びつけて楽しめる。
- 『はやおきおばけ』(せなけいこ)
── 朝起きが好きなおばけのお話。生活習慣とのつながりあり
- 『どうぐのおばけ』(せなけいこ)
── 身の回りの物に命が宿る!「ものを大切にする」気持ちを育む
【3〜5歳以降/親子でじっくり楽しむ応用編】
ストーリー性が強く、ユーモアや知識、発見が盛り込まれた絵本。
- 『おばけパーティー』(ジャック・デュケノワ)
── 色の変化やキャラクターの個性が楽しい。視覚変化に科学の芽もある
- 『おばけの天ぷら』(せなけいこ)
── うさこちゃんとおばけの“天ぷら事件”。展開のあるストーリーが面白い
- 『SPOOKY』(英語仕掛け絵本)
── 英語と仕掛けが組み合わさったハロウィン的世界観。英語の耳にも心にも楽しい刺激
- 『おばけ漢字えほん』(青木健)
── 「山」「川」などの漢字を、意味や成り立ちとともに紹介。
まだ読めなくても、「知ってる!」のきっかけになる1冊
※『おばけ漢字えほん』は小学低学年向けが推奨ですが、イラストや構成が魅力的なため、早くから興味を示す子も多い印象です。
補足コメント
このリストでは年齢を基準に分類していますが、
実際には子どもによって興味のタイミングや楽しみ方は本当にさまざまです。
わが家では、「おばけが好き」という気持ちから、
ちょっと難しそうな絵本にも手を伸ばすことがあります。
ただ、すべてを一度に読むわけではなく、
「今日はここまで」と途中でやめたり、文字を飛ばして絵だけを楽しんだり。
「読む?」「読むのやめる?」と本人に聞きながら、
その時の気分に合わせて自由に楽しんでいます。
逆に、以前読んでいた赤ちゃん向けの絵本を、成長してから改めて読むと、
以前とは違う部分に注目することもあります。
同じ1冊でも、子どもの中で“関わり方”が変化していくのが面白いなと感じています。
選書のカギになるのは、年齢だけでなく、
「その子がどれくらいそのテーマを好きか」。
子どもの“好き”が導く学びには、想像以上の可能性があります。
まとめ
「学び」は、学校の教科書が始まりではなく、むしろ日常の“好き”から自然と育っていくもの。
大人が無理に教えようとしなくても、子どもの「面白い」「もっと知りたい」という気持ちを応援するだけで、学びの芽はたくさん育ちます。
そしてその芽は、いつか教科学習とつながったとき、「知ってる!」「楽しい!」という感覚に変わるのです。