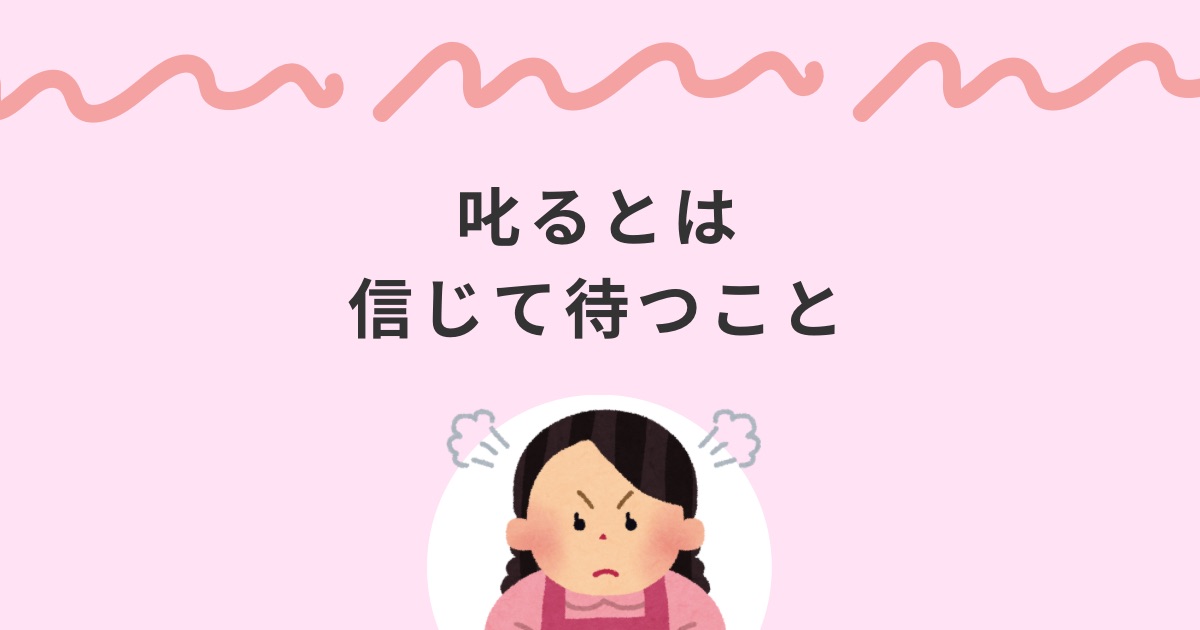1時間泣き叫ぶ子に向き合って気づいた「教育」と「安心」のバランス
この記事で伝えたいこと
- 叱るとは、子どもを変えることではなく“信じて待つこと”
- 泣けば通る世界は、子どもにとっても不安定
- 安心と教育のバランスは、「軸のある関わり」の中にある
「怒る」と「叱る」は本当に違うのか?──教育の限界を感じた瞬間
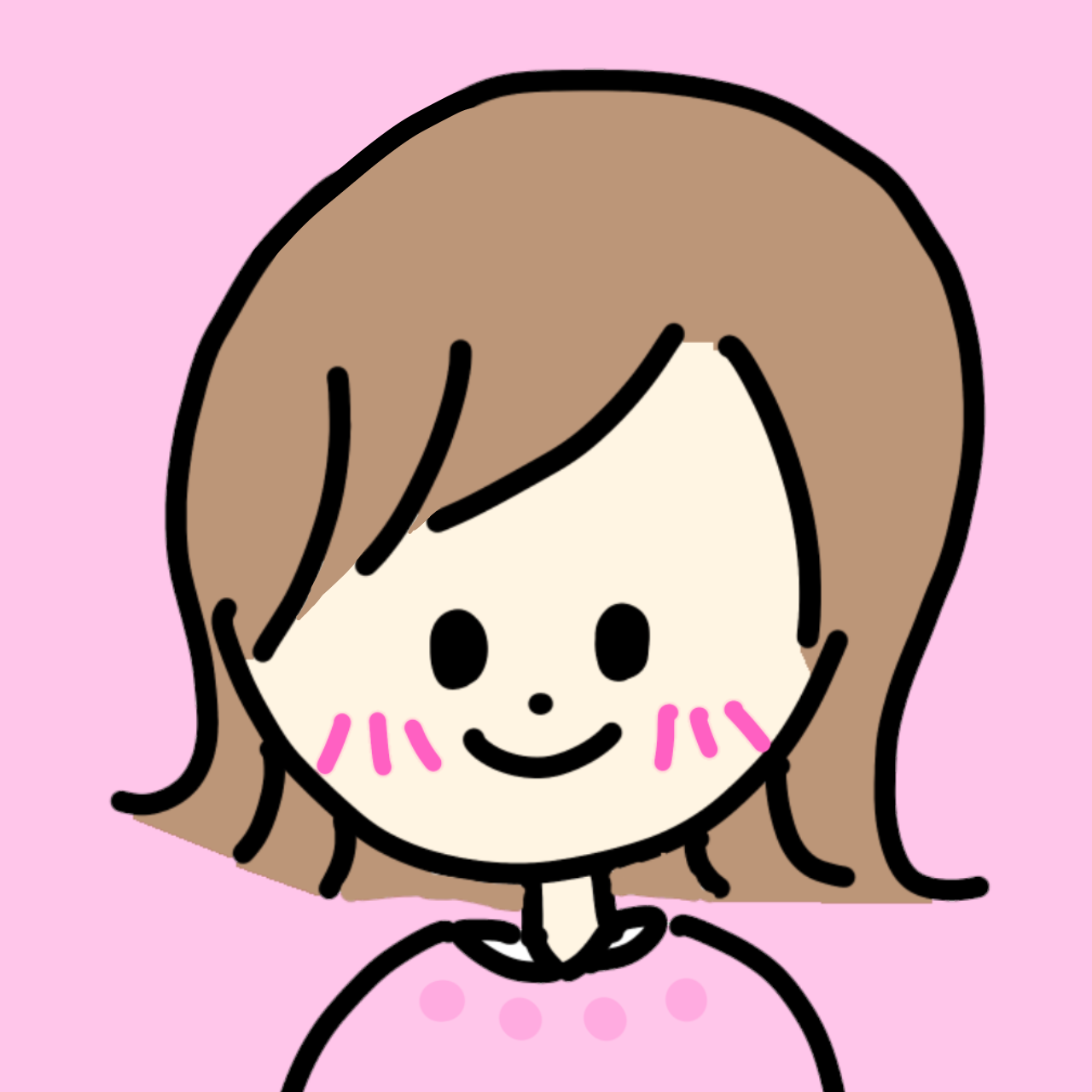
怒るは感情的な爆発、叱るは教育的な働きかけ。
私は教育的に叱るのには以下の2点が必要だと考えました。
教育的に叱るため必要なこと
- 目的を持って関わること
- 落とし所を用意すること
「甘やかし」と「支え」の狭間で揺れた夜
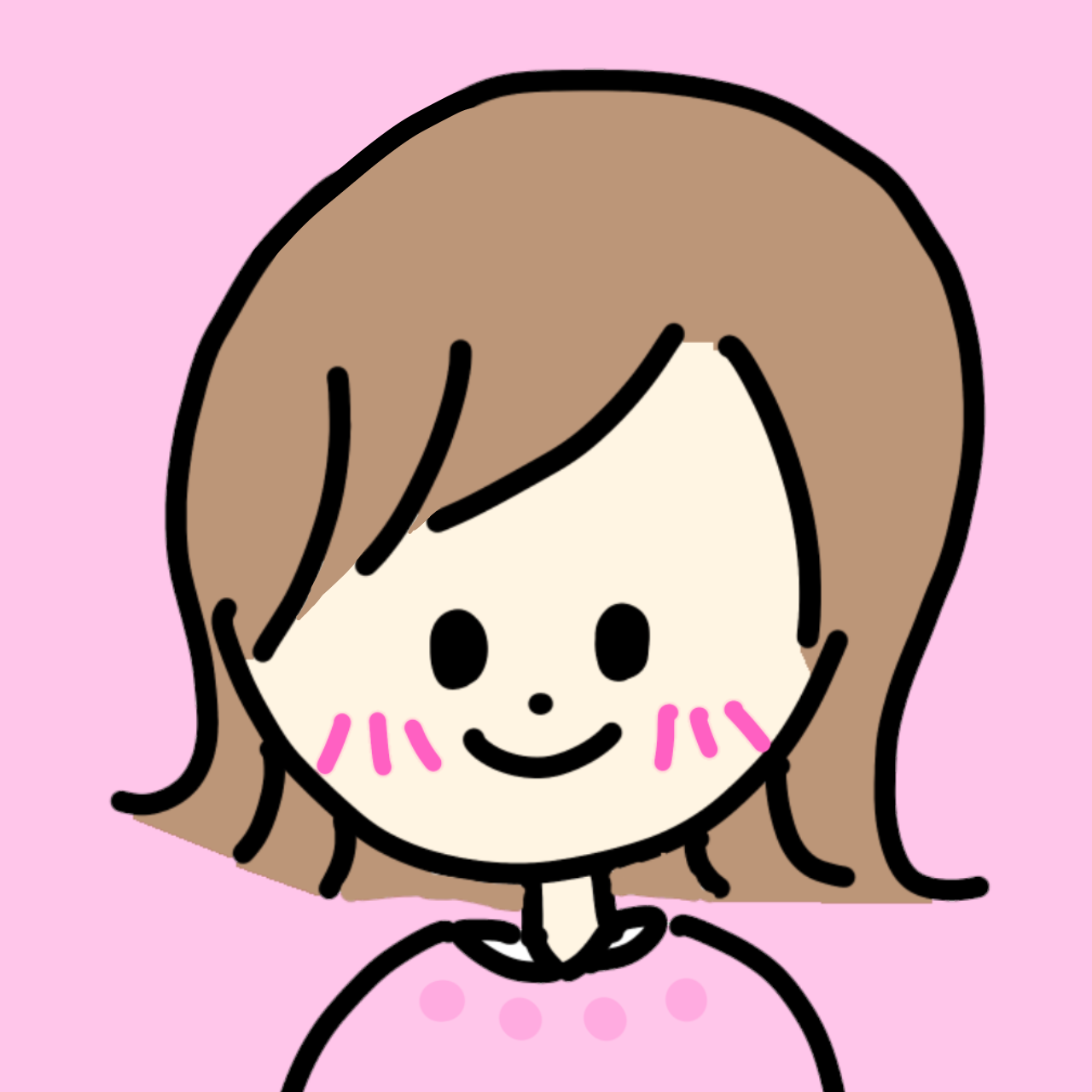
子どもはわがままではない。「誤学習」しただけ
大事なのは、子どもが「悪い子」になったのではなく、
「泣けばなんでも願いが叶う」と学習してしまっただけだということ。
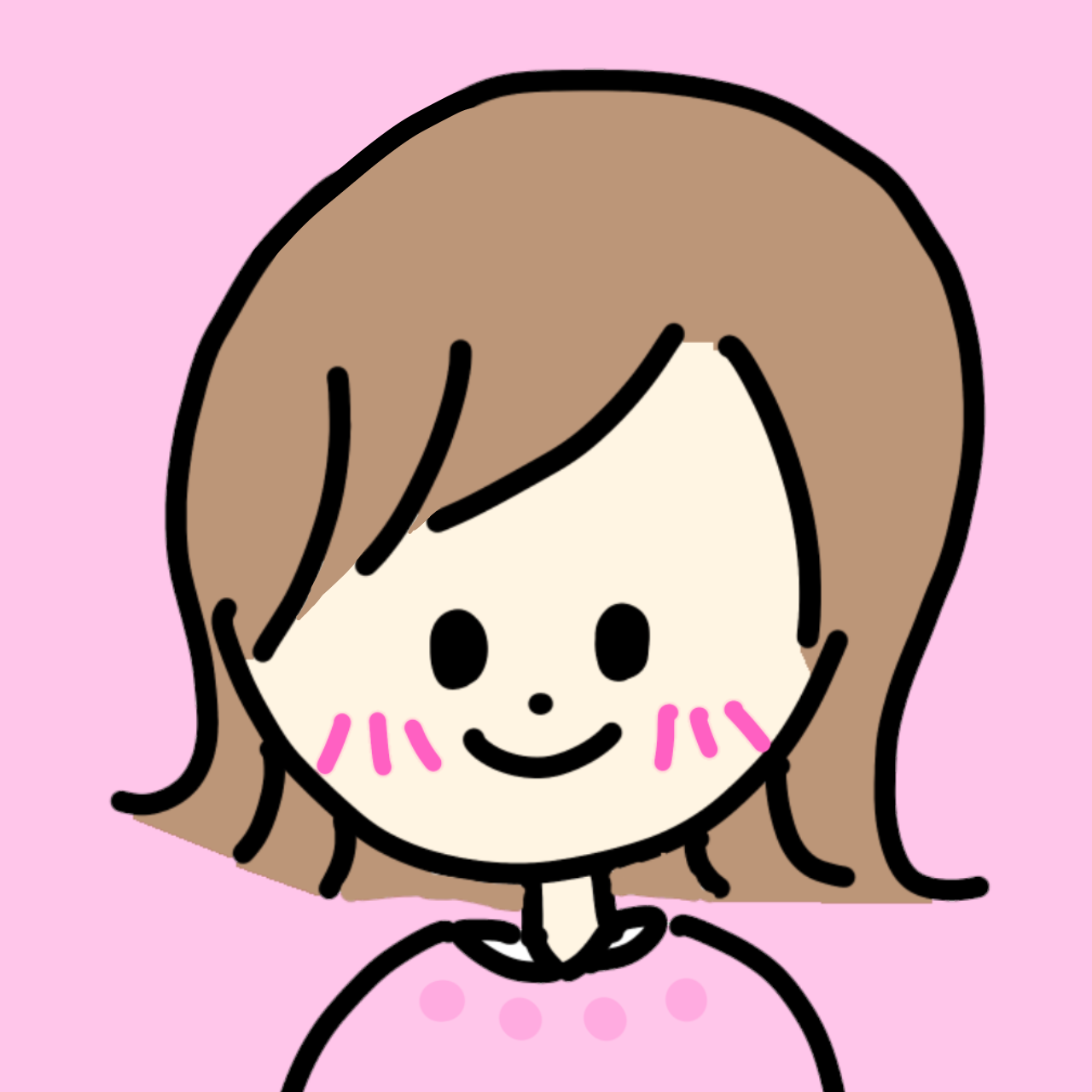
それが今回、私が「叱る」という行動を取った理由。
2歳の子に言葉で言い聞かせても、すぐには伝わらない。
だからこそ、「泣き叫んでもパパは一緒にリビングへ行かない」という行動で示す必要があった。
「反応しない」一貫性と、あえてつくる“落とし所”
1時間近く、子どもは泣き続けた。
私は眠くて限界だったけど、ずっと頭をフル回転させながら「今、声をかけるべきか?」を見極めていた。
そして、泣き声のトーンが変わり、「パパ!」から「ママ!」に変わったタイミングで初めて声をかけた。
ママとぎゅーする?ねんねする?
子どもはまだ「パパがいい」「ねんねしない」と言ったけれど、そこに反応しないことを貫くことで、最後は自分から「ねんねする」と言い、抱きついてきた。
「甘え」と「自立支援」は両立できる
正直、この方法が正解だったかはわからない。
でも、私なりの最善の選択だった。
学習しなおすためには、一時的に混乱が大きくなる「再調整の痛み」が避けられない。
そして、朝。
いつもはパパっ子の子どもが、私に手を出して「おはようタッチ」と言ってきた。
「一緒に行こう」と言って、手をつないでリビングへ向かった。
──あの1時間は、ムダじゃなかったんだ。
子どもは“止めてくれる大人”を求めている
泣き叫んで願いが通る世界は、子どもにとっても不安定でストレスだったのかもしれない。
甘やかすだけでは、安心できない。
子どもは時に、「受け止めながら、止めてくれる人」を求めているのだと思う。
叱るとは、子どもを信じて待つこと
叱るというのは、子どもを「ダメな存在」として否定することではない。
むしろ、「きっとこの子は学び直せる」「安心できる関係を築ける」と信じて待つことだと思う。
そして、泣き声の奥にある子どもの不安や願いに、耳をすませること。
昨夜の体験は、叱ることの本当の意味を少しだけ教えてくれた気がする。